大学の先生は「自分は研究者だ」と思っている?
前々回(スタンフォードで痛感、教員はラクじゃない)と前回(さすが世界トップ層?上から目線の学生たち)では大学教員の仕事のひとつである教育について、スタンフォード大学経済学部、特に僕自身を例にお話しした。
ちょうど最近日本では、国公立大入試方式の改革に関する教育再生実行会議の議論(そこで疑問視されるのは、現行の学力、ペーパーテストのあり方で、それに対して「人物本位」、「本質的な能力を測る」選抜方法を模索したいということらしい)が注目を浴びたようだが、関係のありそうな「アメリカのトップ校における教育」の話も、これで思いのほか興味を持ってもらえるかも?
なんてひそかに期待している。 そういえば、この連載では最初にも、まさにこの議論に通じる「大学院の選抜」、教員の事務仕事を取り上げたのだった(「求む、ガリ勉!」アメリカの大学のやり方)。
ちなみに、大学教員としての仕事には、教育、研究、様々な事務とおおまかに三つある。そろそろ残るひとつ、研究のことを書きたかったところなので、今回は「お仕事としての研究」についてお話ししていきたい。
大学教員といわれたときにまず思い浮かぶのは、教授ではないかと思う。
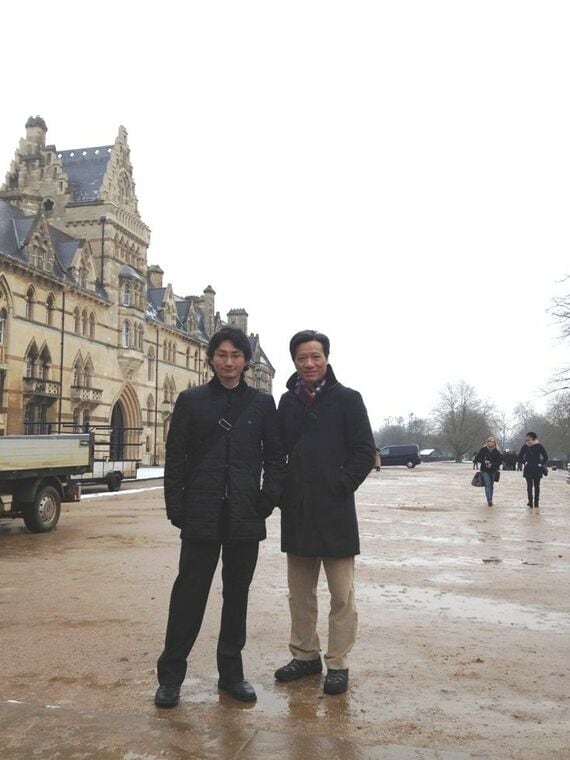
……が、実を言えば、彼らやその亜種(助教授および准教授)は基本的に研究重視の人々だ。彼らの中には、自分のことを「大学教員」というより「研究者」だと思っている人のほうが多いのではないかと思う(※大学教員のポジションは前に説明したとおり、教授とその亜種のほかにもある)。
もちろん大学の性格にもよるし、環境、その他からくる違いはいろいろとあるが、ここでは日本における大学論議の中でも日米比較の対象とされやすい、アメリカのトップスクールを念頭に話を進めたい。
※そういえば「トップ校」という言葉を何気なく使っているけれども、個人的にはこれに違和感があったりする。学生として勉強するにしろ、教員として研究や教育をするにしろ、一次元的な物差しで「上下」を持ち出すのは趣味が悪いかもと思っている。かといってこの「上下」の存在を完全に否定するのもウソくさい。このへんのことについての僕の現在の考えも、いずれ書いてみたい。


































無料会員登録はこちら
ログインはこちら