私は、これまでたくさんの子どもたちを指導してきましたが、彼らには多くには、ある共通した特徴があることがわかったのです。その1つが、「間違えることを恐れている」ということです。ですから、授業で当てても「わかりません」と答えるか、前の生徒と同じ答えを言います。そして間違えると「しまった!」という顔をします。これは何も勉強ができる子、できない子にかかわらず全体的にあることなのです。
きれい事では子どもの心に届かない
負けず嫌いな子になると、さらに極端な反応をします。そこで私は、間違えることの大切さを話すのですが、ただ普通に「間違いは大切だ」「失敗は成功の元」と話をしても具体性がなく心に届きませんし、ただきれい事のように受け止められがちです。そこで、次のような話をするのです。
私:「あのね、失敗や間違いというのは、めちゃくちゃ大切なんだよね。たとえば、これから100点満点のテストを2人にやるとするね。A君が80点で、B君が20点だとする。そのときの2人の気持ちはどのような感じだと思う?」
生徒:「A君はよかった、B君はダメだったという感じです」
私:「そうだね。では次に、2人はその後、テスト直しのときどういう気持ちでやるかな?」
生徒:「A君はたった20点分だから、前向きにやって、B君は悪い点数に落ち込んでいて、あまりテスト直しをしたくないと思います」
私:「そうだよね。それが普通だよね。でもね、この普通が間違っていて、実はその逆が正しいんだよ」
生徒:(え! どうして? という顔をする)
私:「2人に間違えたところを先生が教えてあげるとするね。そうするとA君の場合は、間違った20点分を学ぶだけだけど、B君は80点分も学んで、そのぶん伸びることができるよね。すると塾で同じ月謝を払って、B君のほうが4倍得しているよ。しかもB君の成長率はA君の4倍だ!」
わけのわからないへ理屈のような話ですが、生徒は「なるほど」と感じてくれます。つまり、最終的テストでは間違いや失敗はないほうがいいのですが、プロセスでは逆に間違いや失敗がたくさんあったほうが、成長するのです。
このことを徹底して子どもたちに教えていかなくてはなりません。ですから「失敗は成功の元」という程度の話では、子どもたちの心には入っていかないため、あえて私は「失敗を量産する」という言葉を使っているのです。これくらいの言葉で話をしてちょうどいいぐらいでしょう。
星野さんの娘さんは、負けず嫌いであることも手伝い、間違える自分、わからない状態でいる自分を恐れ、それを周囲の誰にも言えずにきたのではないかと思います。そして、うそをついてしまう状態になってしまったということでしょう。
親御さんがされた、「うそがわかったときは、強くしかることをせず言い聞かせる形で対応し、自分のためにならないことや、成績が悪くてもしからないから、一緒に頑張ろうと伝える」というご対応はとてもいいですね。そこから、一歩前進し、「錯覚に陥っていること」「間違い・失敗の量産」のお話をしてあげてください。娘さんは、またぐんぐん伸びていくことでしょう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

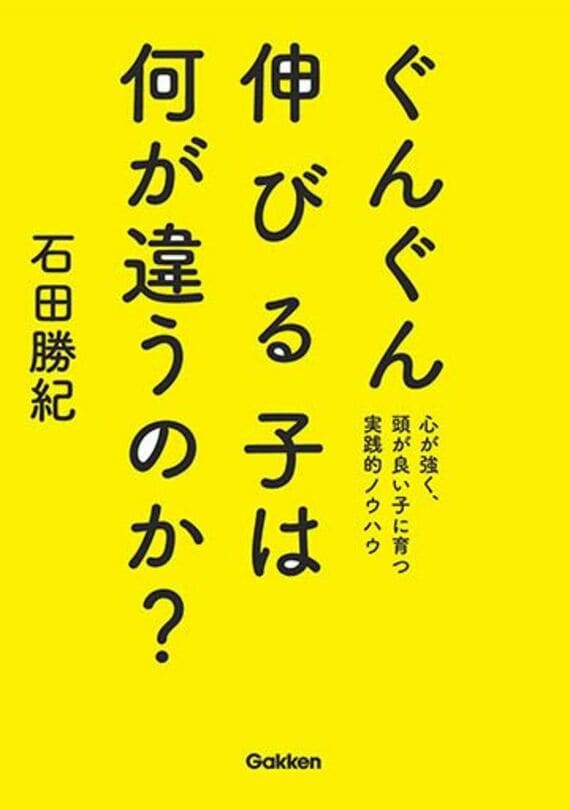






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら