
日本人が日常的に使っているものの中には、外国人をとりこにするような素晴しいものがたくさんある。和包丁もそのひとつかもしれない。私が所有している唯一の和庖丁は、私にとっての相続財産みたいなものだ。その和包丁は7年前、当時22歳だった私が鹿児島で外国語の教師をしていたときに、隣町に住んでいた外国語教師からお別れの品としてもらったものだ。
引っ越しの手伝いに行ったら、その人は少し照れながら台所の流し台の下の戸棚から黒檀色に磨かれた木の柄のひどく錆び付いた和包丁を取り出して、それをくれたのだ。彼女よりも手入れをしっかりするという条件と共に、私は人生初めての和庖丁を承継した。
見た目からして美しい
あのときからこの1本の庖丁には、さまざまな面でとても世話になっている。料理好きの私が台所で使うだけにとどまらず、以前から日本の伝統工芸に引かれて日本語を学んでいた私にとって非常に大きな刺激となり、 人生をより一層豊かにしてくれた。
最近、京都にある庖丁の名店「有次」とめぐり会い、庖丁作りの歴史や、伝統、職人たちの熱意を紹介する『京都・有次庖丁案内』を翻訳する機会を得た。この本は1冊に日本語と英語の両方が掲載された珍しい形態の本だ。以前から和食の勉強を通じて有次のすごさは聞いていたので、この依頼が来たときはまるで夢がかなったように感じた。
さて、私のような外国人にとって和包丁の何がそんなに魅力的なのか、少し説明してみたい。初めて和包丁を見たときは、まずその美しさに引きつけられた。細くて、つやっとした刃渡りに木と骨と鋼の合わせたパレットが、まるで美術作品のように思えた。
加熱と冷却の繰り返しの中で何回も叩かれた後の刃面には鉄の層まで見える。僕は陶芸を習っていたので、素朴な色合いと形を持つ備前焼や丹波焼き、繊細な模様が特徴な有田焼や薩摩焼を始めとする日本の焼き物や陶器には以前から憧れていた。地球(つち)の中から職人の手に渡り、その手から燃える窯の心(なか)へ。そして、窯から出てくるまでの緊張感……。粘土や鋼が職人の知恵と、気持ちのすべてと共に窯に送られ、よみがえるのである。


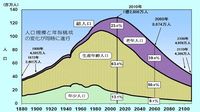

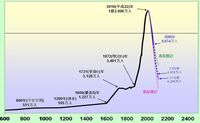





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら