その日、帰り道を歩きながら、それぞれの包丁は本来、料理において単一の仕事をするために作られたもので、和食と和包丁は切り離せない関係にあるのだと考えていた。しかも、職人の情熱というものは、材料を調理するのに使う道具からできあがった料理にまで通じるものだ。こういった共生関係があるからこそ、和食は和包丁で作られるのである。
和食に対する興味がどんどん膨らんでいったおかげで、私の食生活は魚を中心としたものとなり、感謝を込めて魚を食べきり、無駄遣いをせずに自炊するようになった。その結果、冷蔵庫の中が魚の3枚おろしや、中落ちから取った出汁でいっぱいになることがあり、そのたびに友達をアパートに呼んで食事会を開いた。
こういう集まりを頻繁にすることで、台所やアパートの中をつねに整えておく習慣が身に付いた。そうして気づいたころには、いつも周囲を整えるようになっていた。庖丁の手入れを丁寧にすることは、料理の素材だけでなく、それを使って料理を作る人にも影響を及ぼすのである。
包丁をめぐる忘れられない風景
さて、友人の小出刃を受け継いでから数年後、夜に阿久根市の旧港を散歩していたとき、その後私の記憶にいつまでも残る出会いがあった。氷屋や静かに碇泊している漁船を過ぎてから道を曲がり、住宅街に入ると、鉄を石で擦ったり、水を掛たりする聞き慣れた音が耳に届いてきた。その音がするほうを見ると、台所から道にもれた明かりでほんのりと照らされた闇の中で、水いっぱいのバケツに砥石を置き、しゃがんで庖丁を研いでいる男性の姿があったのだ。
子供たちの泣き声や、台所で皿を洗うガチャガチャした音が、刃渡りが砥石の表面を上下に滑らす音と調和し、1日が終わる美しいメロディを奏でているようだった。日本で生まれ育っていない私にとっては、それはとても文化的に意味深いことだったので、その光景を目に焼き付けるためにゆっくりと歩いた。この体験は、日本の家庭における和庖丁に対する尊敬と、普遍性を語る象徴的な出来事として、日本が好きな外国人の友人たちによく披露するエピソードとなった。
最近は意識の高い、グルメな消費者がどんどん増えている。そのおかげで、昔から受け継がれているレシピや、地元産の有機農産物などの真価が見直されているほか、きちんと手をかけて料理を作るための調理器具にも注目が集まり始めている。世界一、と言われる和包丁作りの変らぬ伝統には、私だけでなく、多くの外国人が魅力を感じているし、和包丁の人気は今後世界でもっと広まることだろう。
和包丁を手に取れば誰でも、それが使う側の気持ちを最も考慮した職人が情熱を込めて作ったもので、大切に使われるべきものだとわかると同時に、まるで歴史の一部を握っているような感覚を得るだろう。私には、友人からもらった和包丁が自分の人生における歴史の一部となった。そういう気持ちを与えてくれた和包丁と、その伝統にただ驚くばかりだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

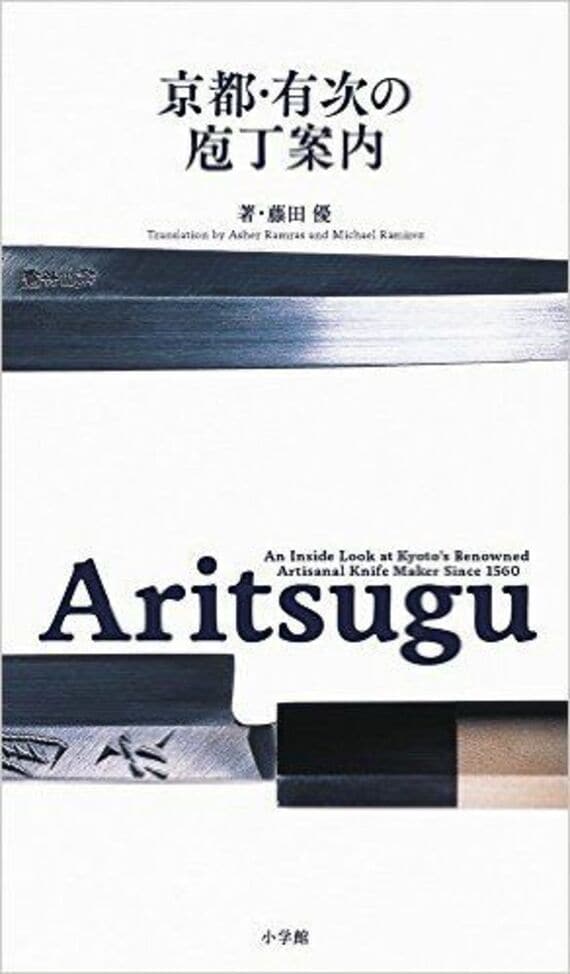

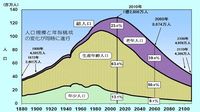
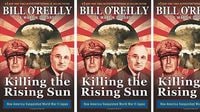
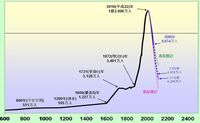


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら