「かつては毎年数人の死者が…」「被害は減ったが生息域は拡大?」茂みに潜む、実はコブラより攻撃力の高い《沖縄の毒ヘビ》驚きの"実態"

沖縄のヘビと聞いて思い浮かぶのは、きっとハブだろう。「ハブ=沖縄の毒ヘビ」というイメージは全国的にも知られているところ。鹿児島県・奄美群島と沖縄県・沖縄諸島の特定の島々に生息し、猛毒を持つハブ。沖縄旅行のお土産屋さんで、ハブ酒の大瓶の中でグルグルととぐろを巻いたハブと目が合った人もいるのではないだろうか。
ハブは人の命を奪うことすらできる毒ヘビとして恐れられるだけの存在かと思いきや、お土産グッズのキャラクターになったり、地元特撮ヒーロー番組の悪役キャラのモチーフになったりと、そういう意味では「地元の親しまれ動物」としての一面も持つ。
ハブの生態や被害について取り上げつつ、沖縄県内で人間とどのように“共生”しているのかを紹介する。
1970年代までは毎年数人の死者も…
実はもう、大部分の沖縄県民にとって、ハブに遭遇することはなかなかない。沖縄の割と一般的な住宅地で生まれ育った筆者は、野生のハブを一度も見たことがない。ハブは夜行性で、茂みの中にいることが多いため、特別な理由が無い限りなかなか出会うことはないだろう(なので、Jリーグ創成期に、あるクラブチームが「練習場の近くにハブが出る恐れがある」という理由で沖縄での練習を中止したことがあったが、少年心ながらにちょっと悔しかった覚えがある)。


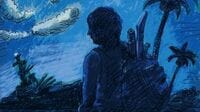




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら