「かつては毎年数人の死者が…」「被害は減ったが生息域は拡大?」茂みに潜む、実はコブラより攻撃力の高い《沖縄の毒ヘビ》驚きの"実態"
ハブ博物公園内をガイドしてくれた企画広報課の宜保裕里さんは「攻撃態勢のコブラはあまり動かないので、ショーなどで扱いやすいと言われています」と話す。たしかに、「コブラ使い」は見たことがあるが「ハブ使い」は今まで一度も見たことがない。

“ハブのいない島”にも出現 拡大するハブの生息域
もともと、サキシマハブは石垣島などを含む八重山諸島に生息し、タイワンハブは台湾や中国に生息していたものだが、貨物の流通に紛れたり、持ち込まれたものが逃げ出したりして、沖縄本島にも局地的に生息している。
近年だと、2024年に「ハブのいない島」の代表格だった宮古島の港で、死んだ状態のサキシマハブが見つかったことがニュースになった。定着は確認されていないようだが、他の島では定住に至った例もある。
同じくハブのいない島だとされていた粟国島(沖縄本島の西約60km)では2017年に初めてハブが捕獲され、定着・増加していることが判明している。同島の粟国村は、他の市町村同様にハブ対策条例を制定し、咬症事故時の医療費補助や、ハブの潜みやすい住宅の石垣の隙間を埋める補修材の支給を定めた。2024年の粟国村のハブ駆除数は245匹と、沖縄県の市町村別捕獲数から見ても多い方に入る。
外来種のタイワンハブは、1970年代にハブ酒などの原料で持ち込まれ、1993年に初めて野外で発見、1996年に定着が確認されている。2024年の沖縄県のハブ駆除数は約6000匹だと述べたが、そのうち約3500匹はタイワンハブであり、その数で言うともはや主流だ。祖堅さんは「ハブ(ホンハブ)の数はそんなに変わっていないと思うのですが、タイワンハブは増加傾向にあるようです。沖縄には天敵がいなく食物連鎖の頂点の方にいるのが理由なのかもしれません」と説明する。


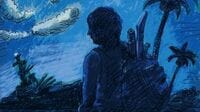




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら