関ヶ原の戦いは「裏切り者を見抜く」教科書だ 「友人、部下、同僚」こんな人物は要注意!
西軍を裏切った大名の動機をあらためて詳しく見ていくと、意外にも「石田三成本人への怨恨」を挙げる大名は少ないようです。
もちろん、石田三成を嫌っていた大名ははじめから家康の側につくでしょうから、それはある意味、当然ともいえます。「関ヶ原の決戦当日をむかえるまでの石田三成は、それなりに西軍をよくまとめていた」とも思います。
とはいえ、石田三成が西軍の大名から好かれていた様子もなく、そうでなければ、これほどの「裏切り」が続出するわけがありません。やはり、「石田三成に人望がなかった」というのも本当のようです。
もし、徳川家康に匹敵する人望を石田三成がそなえていたら、戦いの結果は違っていたかもしれません。
「裏切りは当たり前」だった戦国時代
現代に生きる私たちの価値観では、「裏切り」と聞くと非常にマイナスイメージがあります。しかし、当時はむしろ「裏切りが当たり前」の時代でした。
自分たちが「生き残る」ために烏合(うごう)離散は日常茶飯事。このころはまだ「武士道」などという言葉すら存在していません。下克上の戦国時代を生き抜いてきた大名たちにとって、裏切りは特別なことではなかったのです。
もうひとつ、多くの裏切りが起きた背景には「徳川家康の画策」がありました。家康は情報網を駆使して事前に周到な策をめぐらせ、裏切りを誘発していたのです。
この時期、家康は西軍に味方しそうな各地の大名たちに膨大な数の手紙を書き送り、決戦の前から懐柔していました。その結果、西軍には家康に内通した大名たちも多かったのです。
石田三成は、そうしたことに警戒はしていなかったのか。怪しい動きを察知することはできなかったのか。裏切る人の動機はさまざまありますが、結果からすれば、内通を見抜けなかった石田三成は脇が甘かったと言わざるを得ません。
このように関ヶ原の戦いを見てみると、現代にも通じるさまざまな教訓を得ることができます。「勝利する者」は事前に周到な準備をし、逆に「敗者」の側から見れば、裏切る者には何かしらの「動機」があり、それを冷静に見抜けなかったことが敗北につながりました。
日本史には、このように人間関係を考えるヒントが詰まっています。ぜひ歴史を学び直すことで、ビジネスや実生活で生き抜くための「人間関係の武器」を手に入れてください。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
















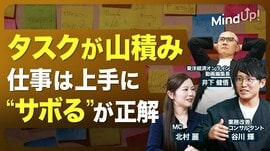















無料会員登録はこちら
ログインはこちら