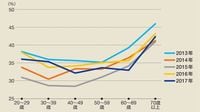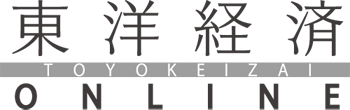死者をないがしろにする日本はおかしすぎる いとうせいこう×中島岳志対談<前編>

3・11以降、ふたりが考えていた「死者」の問題
中島 岳志(以下、中島):私は、2月に『保守と立憲 世界によって私が変えられないために』(2018年)という本を出しました。この本は、3・11以降、さまざまな媒体に書いた評論に、書き下ろしの章や立憲民主党代表・枝野幸男さんとの対談を加えて1冊にまとめたものです。その意味では、3・11が起点になってできた本でもあります。
3・11のとき、いとうさんと僕は、ほとんど同時に「死者」という問題を考えていたと思います。地震があってすぐ、私は、この本にも収録されている「死者と共に生きる」という文章を書き、共同通信で配信されました。それからしばらくして、朝日新聞の書評委員会の後に、いとうさんと飲みながら話をしましたよね。その場で、「今、どういうお仕事をされているんですか」と聞いたら、『想像ラジオ』のモチーフをお話しくださった。それが死者の問題だというので「同じことを考えていらっしゃるんだな」と思ったんです。『想像ラジオ』は2013年の刊行ですから、あれからもう5年も経ったんですね。出来上がった『想像ラジオ』を読み終えて、ようやくポスト3・11の文学が生まれたことを実感しました。
あらためていまお聞きしたいんですが、あの頃のいとうさんが死者の問題に向き合おうとした背景にはどのような思いがあったのでしょうか。
いとうせいこう(以下、いとう):3・11で多くの人々が亡くなったという途方もない事実に対して、僕も含めて誰もが失語症のようになってしまったと思うんです。テレビからは同じような映像が繰り返し流れてくるけれど、悲惨な映像には実は規制がかかっている。死体が映らないように選ばれた映像をわれわれは見せられているから、何をどのように受け入れたらいいのかもよくわからない。同時に、自分の身内や知り合いを亡くされた方々も、あまりに多くの死者が生まれてしまったがために、自分の身近な人を悼むことも悪いんじゃないかという思いを抱いてしまうような状況もありました。だから、あの状況では哲学というものが必要だったし、僕の場合は音楽が必要だと思ったんです。
そんなときに、ラリー・ハードというアメリカのすごく有名なDJが、音楽配信スタジオのDOMMUNE(ドミューン)でプレーしていて、ット・ット・ット・ットと4つ打ちのダンスミュージックを2時間くらいネットで流してくれたんですよ。それを聴いて3・11の後、初めて生きている実感を持つことができました。これはいったいなんなのだろう。考えみると、死者の側に生者ものみこまれて、リズムというものを失っていたんだということに思い至ったんです。生者も共に死んでいる状態になっていたんだ、と。