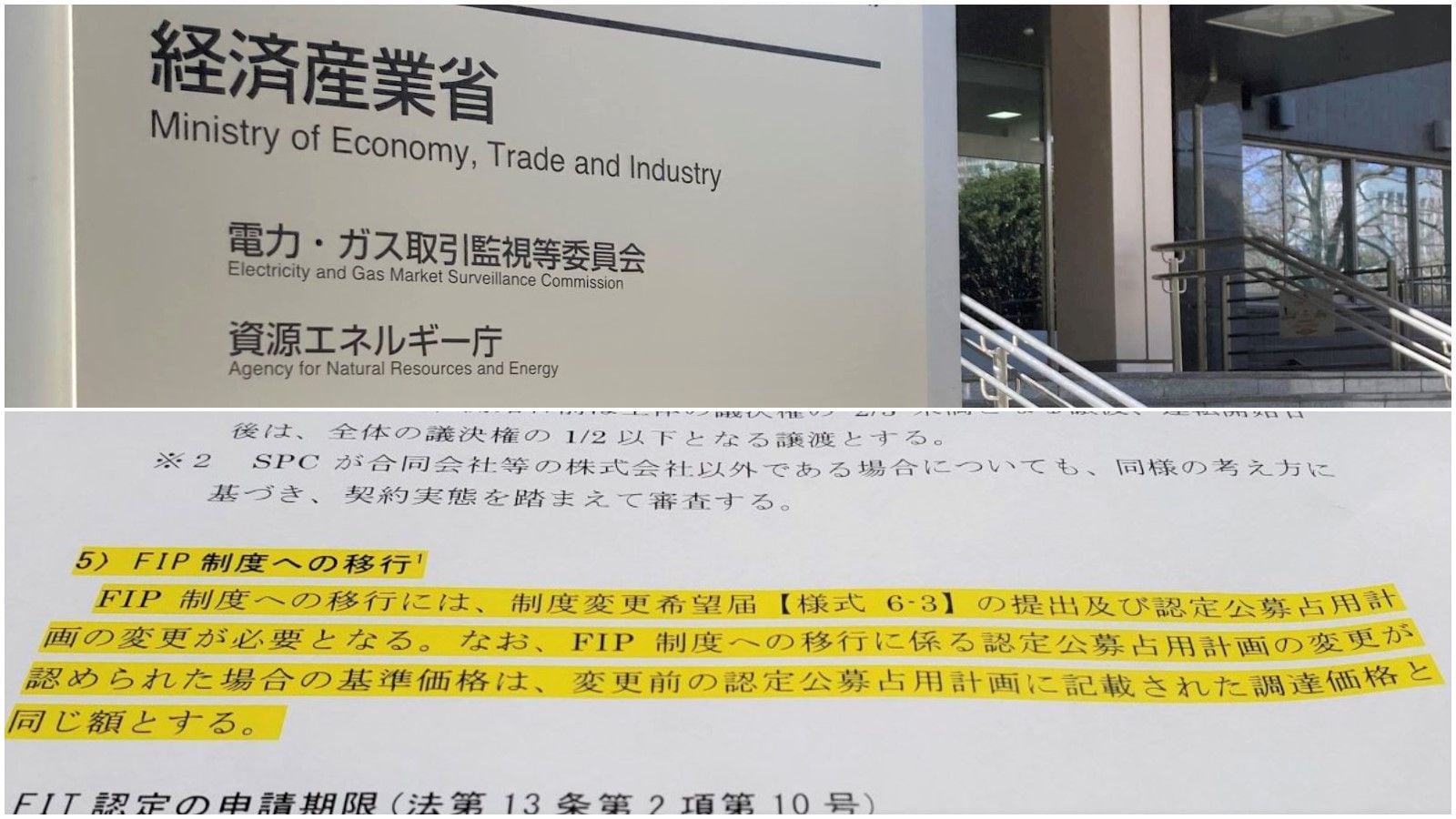
洋上風力発電政策の「迷走」はどこに行きつくのか。資源エネルギー庁による三菱商事連合に対する事実上の救済策をめぐり、ほかの発電事業者が批判を強めている。
国は洋上風力発電を重点的に進めており、これまで国内10の一般海域を「促進区域」に指定。海域ごとに公募を実施してきた。落札した発電事業者はその海域を最大30年間占有できる。
救済策だと指摘されているのは、公募第1弾となった秋田県沖と千葉県沖の3海域における洋上風力プロジェクトだ。この2021年12月の「第1ラウンド」で三菱商事などの企業連合は3海域を総取りした。入札で示した売電価格が他陣営より格段に安いことが決め手となった。
しかし落札から3年余りが経った今、世界的なインフレや円安で資材価格が高騰、入札時の想定コストを大幅に上回る状況になった。目算が狂いプロジェクトは窮地に立たされている。そこでエネ庁が事実上の救済策に乗り出したというわけだ。
ほかのプロジェクトにも悪影響?
3月10日、エネ庁と国土交通省の審議会で公募占用指針の改訂案について審議が行われた。ここで突如、「第1ラウンドのプロジェクトにFIP(フィードインプレミアム)制度への転換を認める」という公募指針の修正案が示された。
ところがこの案が成立すれば、2023年12月と翌年3月に計4海域の落札事業者を発表した「第2ラウンド」以降のプロジェクトの収支が大幅に悪化する可能性がある。
「結果的に第2ラウンド以降の事業者は撤退するところも出るのではないか」(発電事業者)との懸念も広がる。
三菱商事連合など第1ラウンドの前提となっていたのはFIT(固定価格買い取り制度)による売電だ。地域の電力会社に発電した分だけ、固定価格で20年間電力を売ることができる。



































無料会員登録はこちら
ログインはこちら