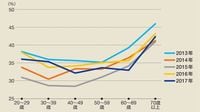死者をないがしろにする日本はおかしすぎる いとうせいこう×中島岳志対談<前編>
いとう:不思議なことだけど、そこにリズムをもたらしたのは、アメリカからやってきた「まれびと」だったわけです。明るいことをしてはダメだとか、笑いはダメだとか言って、お互いに牽制し合っている中で、よそからリズムがもたらされ、音楽がもたらされた。その音楽に対して、被災地の人たちからも「ありがとうございます」「すごく生きる勇気が出ました」といった反応がありました。『想像ラジオ』で、ラジオから音楽がたびたび流されるのは、やっぱりあのときの体験が大きかったからなんですね。
死者論は未来の他者とつながっている
中島:『想像ラジオ』には、「いつからかこの国は死者を抱きしめていることができなくなった。それはなぜか?」という一節があります。

死者の世界は、霊界のようなものとして単独にあるのではない。生者がいるから死者が存在していると。だから、生きている人類が全員いなくなれば死者もいなくなる。いま生きているというこの社会の中に、死者という構成員が含まれている。そういう考え方だと思うんです。
しかし現代社会はそのことを忘却してしまっている。むしろ、まるで忘れることが社会を前に進めることであるかのように、何もなかったように事態にフタをしてしまう。
いとう:そのとおりです。
中島:実際、地震の後には、インフォメーションの言葉や「原発は安全です」とか「頑張れ」といった上滑りな言葉ばかりがあふれていました。でも、あのとき人々が欲していたのは、それとは違った文学の言葉、あるいは音楽のような言葉にならないコトバの世界だった。それをどう紡げばいいのかと、みんなが試行錯誤していました。そんなときに、これも不思議な一致ですが、私もいとうさんも、そして批評家の若松英輔さんも、2月に亡くなった石牟礼道子(いしむれ みちこ)さんの本を読み始めたんです。
石牟礼さんの『苦海浄土』(1969年)を読んで僕が感じたのは、死者を考えることは、過去に縛られるのではなく、時間軸が反転して未来を見ることになっていくということです。
石牟礼さんは、目の前の水俣を書くために、明治初期に起きた足尾鉱毒事件のことを調べ始める。つまり、足尾で亡くなった人たちの声を聞きながら水俣を考え、書いているんです。そしてたくさんの亡くなっている人たち――彼女は「死民」という言葉を使っていますが――から自分は照らされていると言及します。