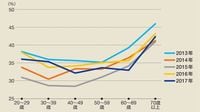死者をないがしろにする日本はおかしすぎる いとうせいこう×中島岳志対談<前編>

中島:『苦海浄土』が出版されたのは1960年代。僕は1975年生まれなので、石牟礼さんがこの本を書いているときは生まれていません。でも、石牟礼さんの言葉を、未来の他者である僕が読んで福島の未来を考えようとしている。石牟礼さんが死者と語り合うこと、そして僕が水俣の死者を想起することが、まだ生まれていない福島の誰かのことを考える、あるいはその人と対話をすることにつながっていく。このとき過去と未来が同時的に出会っているんですね。これが死者の問題だと思ったんです。
いとう:そうなんですよね。死者論は、結局、未来論にもなっている。というのも、いま生きている人と、いま生きていない人とを分ければ、未来の他者も過去の死者も、同じくいま生きていない人になるからです。
いま生きている者だけがこの世界を使っていいのかという問いは、即座に、エコロジーの問題にもなっていきます。未来の誰かのために残そう、あるいは過去からずっと引き継いできたものを引き継ごうとよく言うけど、それは両側に対する死者論を実体験的に語っていることなんですよね。
実際にいま生きている者だけが世界を支配していいのだったら、この世界はとっくに終わっているはずです。そんな当たり前の想像力が働かないと、自分の血を分けた子どもたちだって死んじゃいます。生きるうえでは、ある謙虚さがどうしても必要なのに、どうもあるときから、一気に、取れるものは皆いま取っておこうという発想になってしまったんですよ。
戦後、立憲主義が軽視されてきたのはなぜか
中島:死者の問題を考えるうえで、柳田國男の『先祖の話』(1946年)も示唆に富んでいます。この本で柳田は、「御先祖になるつもりだ」としきりに話す老人のことを書いているんです。
柳田が南多摩郡のあたりを調査していた頃、バス停でたまたま居合わせた老人と話し込むんですね。その老人は生まれが新潟で、若いときに長野で大工仕事を覚え、東京で稼いで南多摩に落ち着いたと言います。彼は郷里から母を呼び寄せて安らかに看取り、材木商として6人の子どものための財産も築いた。あとは死を待つだけ。そんな老人が、柳田に対して「御先祖になるつもりだ」と朗らかに言う。その言葉を聞いた柳田は、先祖になることを死んだ後までの目標にするというのは、いまどき例のない「古風なしかも穏健な心掛け」だと感心するんです。
このくだりを読んで、死者や先祖の問題は、未来志向であると同時に、倫理的な生き方を問いかけてくるものであることを感得しました。ところが昨今の日本は、先祖や死者をないがしろにし、忘却しようとしている。それが、政治がおかしくなっていることにつながっているのではないかと、本を読み直したあとから考え始めました。