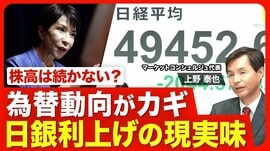教科書に載るほどガチの"シャッター街"の大変化 JINSの田中仁CEOが私財投じるなど民間主導で"衰退した地元"を再生中《前橋》
ところがその繁栄は1990年代から一転します。原因の一つは上越・北陸新幹線の停車駅が隣の高崎市に決まったこと。交通の要衝となった高崎は人口でも前橋を上回り、需要と供給のバランスから民間開発は前橋でなく高崎に集中したのです。
追い討ちをかけたのは、郊外型の大型ショッピングモールの出現です。商圏は郊外へと移り、中心部の空洞化が加速しました。これを物語るのが9つの商店街の核となる前橋中央通り商店街の1日当たりの歩行者数です。1985年には1万5179人を数えたのが2007年には1943人に激減。かつてのにぎわいは幻になってしまったのです。

前橋の起死回生劇はそんなどん底の状況から始まりました。
当初からまちづくりに関わってきた同市の市街地整備課長、纐纈正樹(こうけつ・まさき)さんとにぎわい商業課の田中隆太(たなか・りゅうた)さんに話を聞きました。

「声を上げたのは前橋出身であり、現在も市内に本社を置くメガネブランド『ジンズホールディングス(以下、JINS)』の代表取締役CEO、田中仁さんでした。提言されたのは『ビジョンあるまちづくり』。
それまでも行政でさまざまな手を打ってきましたが、目指す方向を市民とともに定めなければ抜本的な改革はできないと指摘されたのです。そこで官民が協働してビジョンの策定に乗り出しました」
纐纈さんはそう振り返ります。
「めぶく。」と名付けられた前橋ビジョンが発表されたのは2016年のこと。命名したのは前橋出身の糸井重里さんです。
公共空間の馬場川通りを民間資金で整備
翌年には米国・ポートランドに官民で視察に出向き、そのまちづくりを参考にしながらアーバンデザインの策定が始まりました。
異例といえるのは、策定が民間主体で進められたことです。