減塩は本当に健康的?日本に蔓延する減塩至上主義の盲点
つまり、「塩は少ないほどいい」とする考え方には、科学的に見て再考の余地があるのです。塩の摂取量そのものよりも、体質や排出能力など、個々人の代謝状態の方が、むしろ重要である可能性もあります。
減塩がもたらす思わぬリスク
それにもかかわらず、日本では「一律に減塩すべき」との考え方が依然として根強く、実際の平均摂取量は男性で11〜14グラム、女性で9〜12グラムほど。
これをすべての人に対し「6グラム未満に抑えるべき」とするのは、現実的にも心理的にも無理があるのではないでしょうか。
さらに、極端な減塩には思わぬリスクもあります。全米医学アカデミー(NAM)は2013年、「1日5.8グラム未満の塩分摂取では、健康改善効果を証明するには不十分」との見解を発表しました。これは、国際的な減塩政策の再検討を促すきっかけにもなりました。
減塩の影響で見過ごせないのが、ミネラル不足です。ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウムなどは、体の電解質バランスを整え、代謝や神経伝達、酵素の働きを支える「補酵素」のような存在です。こうしたミネラルが不足すれば、体内のエネルギー生産が滞りやすくなり、代謝が落ちて疲れやすくなります。
まるで新幹線が各駅停車になってしまうようなイメージです。
とくに若年層では、亜鉛不足による味覚障害が増えていると指摘する専門家もいます。「減塩によってミネラル摂取が減ること」が、その一因となっている可能性も否定できません。
時代とともに研究が進み、「塩=悪」という構図はもはや絶対的なものではなくなっています。塩を必要以上に怖がるのではなく、「どんな塩を選ぶか」「どう摂るか」を見直すことが、今の私たちに求められているのかもしれません。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

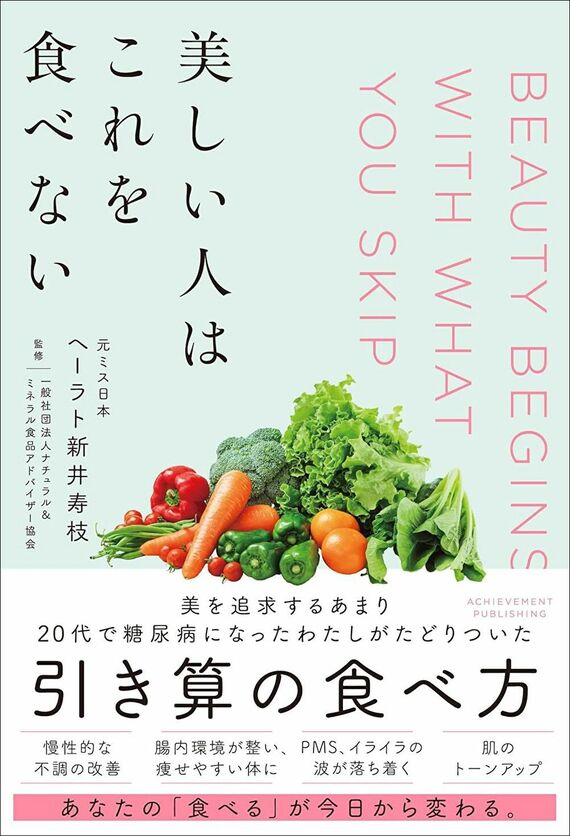






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら