「危険な職場」と同じように客観的にハラスメントがあるのに、労働者がストレスを感じていない状態を表す象限が、右上の「ブラックな職場」です。
この職場ではハラスメントを許容している空気があり、労働者も「このくらいならハラスメントに当たらない」「この基準を達成できないならこのくらいの叱責は当然」という独自の基準を有しています。
この職場ではハラスメントに対して声を上げることが難しく、被害を受けている労働者もそれを当然のこととして受け入れているため、放置していると「危険な職場」に移行してしまいます。
そのため、第2、第3のハラスメントが起きやすい環境です。
それぞれの職場で「健全な職場」を
左下の象限は、「ぬるい職場」です。
この職場では、労働者はストレスを感じていますが、客観的に見てハラスメントとはいえないという状況です。労働者は適切な指導を受けているのに被害意識を強く感じたり、労働者としての義務を果たさないまま権利について主張するといった行動に出やすくなります。
また、懸命に自身の仕事に取り組む労働者に対して、周囲が「それはやりすぎだ」「あなたのせいで私たちまで頑張らなければならない」と主張するときもあります。
結果として、やる気のある社員が離職しやすく、さらにぬるま湯度が上がる悪循環が生じます。
労働者はハラスメントについても誤った認識を持っていることがあり、「自分が傷ついたのだからハラスメントだ」という主張がその典型です。
このような職場では、主観ではハラスメント被害を受けている労働者が加害行為を無自覚に行ったり、やる気のある社員が周囲との温度差にじれて、きつい物言いをするなどのトラブルが生じやすくなります。
仕事として任された範囲や責任、どこまでが適当な業務指導の範囲なのかという認識が労使間・労働者間でブレているので、それを合わせるための対策が必要です。
●ハラスメント事案を判断する際は、客観的相当性、主観的なストレス度を軸に整理する
●ハラスメントの四象限マトリクスは、緊急度の高い順に「危険な職場」「ブラックな職場」「ぬるい職場」
●それぞれの職場で「健全な職場」を目指す必要がある
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

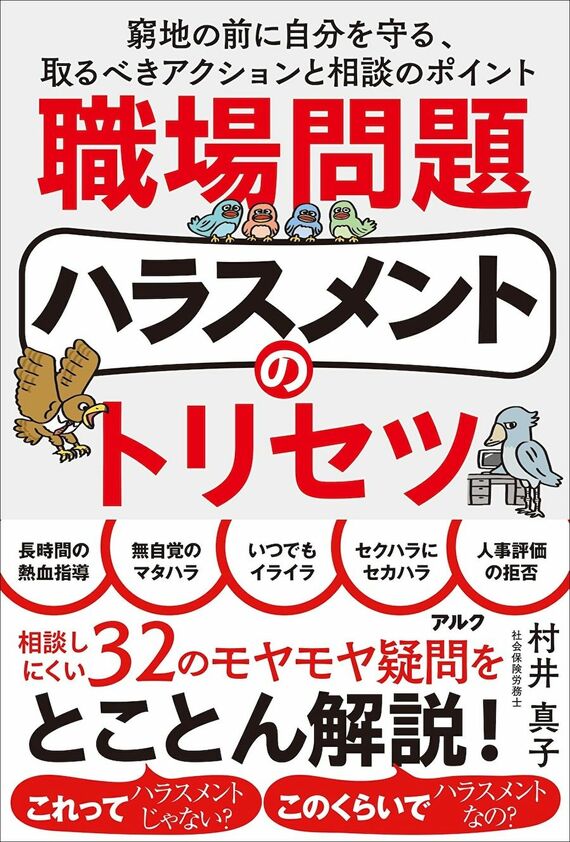






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら