「板で仕切られただけのブース」「妖しい利用目的の人も」…は今や昔の話! ネカフェ業界で独走「快活CLUB」独り勝ちの要因
快活CLUBはこういった高単価と引き換えに、「脱・ネカフェ化」ともいえる、従来のインターネットカフェにない店舗づくりを行ってきた。この施策がインターネットカフェを利用してこなかった女性層・ファミリー層、ビジネスパーソンを呼び込んだことは、疑いないだろう。
一方で無料サービス(モーニング・タオル使用など)の終了で、既存顧客にはサービスダウンとなったものの、むしろ新規客層のために「顧客を静かに選んだ」のではないか。

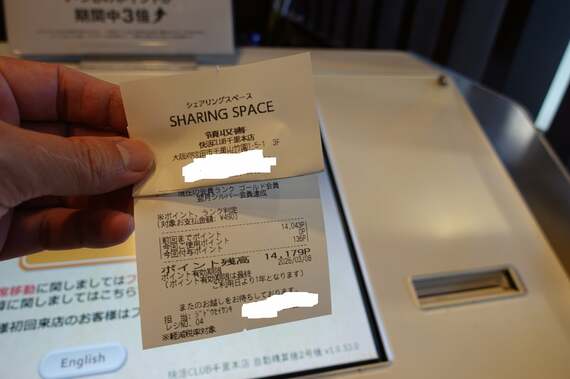
ネカフェ専業からシェアリング業態へ
近年では、快活CLUBも自社をインターネットカフェとしてだけではなく、ビジネスシーンにも使える「シェアリングスペース業態」と位置付けている。
コロナ禍のさなかにも「カフェではなくシェアリングスペース」との姿勢を貫き、休業要請を押し切って営業を継続。批判を浴びたことも記憶に新しい。
ただ、コロナ禍ではオフィス分散、「三密防止」の観点からコワーキングスペース・シェアリングスペースが爆発的に成長した。快活CLUBはレッドオーシャン(成長なき過当競争)のネカフェ業態から、コロナ禍で成長産業となった「シェアリングスペース」業態への移動を志向したようにも見える。
そういった意味で、コロナ禍で「快活CLUB=シェアリングスペース」として知名度が上がったのは、ある意味幸いだったのかもしれない。快活CLUBが今後も「脱・ネカフェ」ともいえる施策で新規客層を掴み続けるか、注目したい。
後編記事「減少の一途『ネカフェ』しぶとく生き残る店の正体」では、快活CLUBの親会社であるAOKIとの関係や、「独り勝ち」となるまでの「ネカフェ業界史」について、掘り下げてみよう。一見して別業態に見える「インターネットカフェ・シェアリングスペース+紳士服」には、どのようなシナジー効果があるのだろうか?
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら













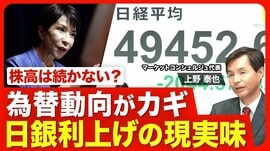


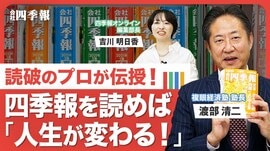




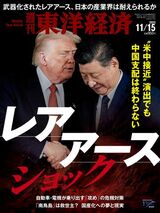









無料会員登録はこちら
ログインはこちら