医師不足に拍車をかける「偽りの働き方改革」 "自己研鑽""宿日直"で働かせ放題という現実
2024年7月、男性医師は労災認定を求める訴えを東京地裁に起こした。妻は「現在小学生になった子供ですら『ずっと帰ってこられず病院にいなきゃいけないのに、働いていないと言われるの?』と言っています。夫が労災認定されないなら、何のための労災制度なのでしょうか」と話す。
働き方改革に逆行
「自己研鑽の拡大解釈の横行と不適切な宿日直許可の濫発は、いずれも労働時間を短く見せるごまかしであり、医師の働き方改革に逆行するものだ」。勤務医の労働組合「全国医師ユニオン」の植山直人代表は実態を語る。
ごまかしを改めて適正化しようとすれば、不払い労働に対する賃金の支払いが必要になるが、「診療報酬の支払額が十分でない中で、良心的な病院ほど経営的に逼迫することになる。一方で無償労働を強いる悪質な病院が有利になるというモラルハザードが生じる」と警鐘を鳴らす。

民間病院の幹部は、「医師不足の中で労働時間を適正化しようとすれば、土曜外来の閉鎖や夜間救急の受け入れ停止などをせざるをえない。そうなれば収入は減少するため病院の経営難につながる」と話す。
ごまかしで乗り切ろうとする医療界に対して、若手医師からは冷ややかな声が聞かれる。「医者だって普通の人間。こんな働き方をしてまで地域医療を守りたいという若手は減っている。働きやすい職場を求めて美容医療に流れる友人も出てきた」(内科の専攻医)。
医師の長時間労働は、医療安全の低下の面からも患者、国民に直結する問題だ。医師の自己犠牲を前提とした診療報酬体系の見直しは欠かせない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




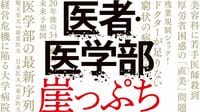


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら