
PTAの最初のミッションは親たちが学校を監視すること
――お節介というとき、ふと思いつくのがPTAです。共働き世帯の増加によって、ベルマーク集めの非効率さとか、その活動の繁雑さを嫌う人も増え「不要論」すら出ていますが……。
PTAは戦後、僕たちが小学生の頃にアメリカから入ってきた制度だと思います。それまでの軍国主義教育に対する反省から、親たちは民主的な学校教育を求めていた。でも、教員たちの多くは戦前戦中と同じ人ですから、軍国主義教育しか知らない。民主主義教育がどんなものか、教師も親たちも見たことがないんです。
だから、教師と親たちが相談して、民主教育とはどういうものかを議論して、それを手探りで実践していった。教師たちの中には戦前と同じように子どもを殴りつけて訓育するのが教育だと思っている人もいましたから、親たちは学校を監視する必要があった。それがPTAの最初のミッションだったと思います。

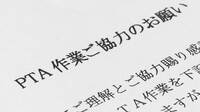





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら