松本市立明善小PTAが「解散を決断」した訳、道のりは決して簡単なものではない 保護者ボランティア組織のあり方と運営のコツ

任意加入制に移行したところ、加入率は50%に
「きっかけは、2022年3月、保護者から届いた一通の退会届でした」(石曾根氏、以下同)
長野県松本市にある明善小学校のPTAは、子どもが入学したら自動的に入会する仕組みだった。PTA本部の下に学年部、厚生部、広報部、施設部、支部活動部と5つの部会があり、半強制的に参加が強いられてきた前例踏襲型の組織だったという。
2021年度に同校PTAの副会長、2022年度からPTA会長になった石曾根氏は、退会届が届いた背景には「PTA活動に負担を感じている保護者が少なくない」「委員がなかなか決まらない」など、組織のあり方や運営方法に課題があると判断し、PTA活動の縮小を提案。校長、本部役員と議論を重ね、5つの部会を4つに減らし、PTA会費も年3000円から2500円に値下げした。

松本市立明善小学校保護者ボランティア代表。2021年明善小学校PTA副会長、2022年〜2023年同校PTA会長。2024年4月より、保護者ボランティア代表に。5人の子どもの父親
(写真:石曾根氏提供)
石曾根氏は2023年度もPTA会長をつとめ、全保護者に対し加入・非加入の意思確認を行い、組織のさらなる簡略化を図っていくことを周知した。
「結果、加入率は50%になりました。予想していたよりも低い数字でしたが、非加入を選択した保護者からは、『加入はしないけれども、草刈りなどこれまでPTAが担ってきた保護者活動には参加します』という声も多く聞かれました。ちなみに、非加入を選択した理由は、『役員になりたくないから』という声が多かったです」
松本市P連からも退会を決意
保護者の声を受け、これからのPTAのあり方について、校長、教頭、PTA担当教員、本部役員と何度も話し合いを重ねたという石曾根氏。その回数は7〜8回に及んだという。その結果、現行のPTA組織を解散するという結論にいたった。
明善小学校PTAは当時、松本市のPTA連合(以下、松本市P連)に加入していた。PTA解散後も市P連など、ほかの団体とさまざまな情報共有や連携は大切だと考えた石曾根氏は、松本市P連にPTAを解散した場合や今後新しい形に変えて活動した場合なども、市P連への加入を継続することは可能かどうかを相談した。
しかし、松本市P連からの回答は、「新しい形がどうなるかわからない現状では、継続が可能かどうか決めることはできません」というものだった。

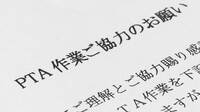






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら