松本市立明善小PTAが「解散を決断」した訳、道のりは決して簡単なものではない 保護者ボランティア組織のあり方と運営のコツ
また、『子育て、家事、仕事を最優先していただきながらできるときにできることを行ってください』と呼びかけつつ、7月の授業参観日の学級懇談会後にベルマーク集計作業の協力を募ったところ、各クラス約半数の保護者が残って作業してくれました。今のところ、困っていることはありません」
石曾根氏は続ける。
「一方で、デメリットとして感じるのは、保護者間の交流が少なくなったことでしょうか。また、松本市P連を退会して他校のPTAとの交流が少なくなり、地域の学校やPTAの情報が入りにくくなったこともあげられます。ただ、松本市P連については、昨年度まで加入していてある程度のネットワークができています。必要な情報はこちらからとりにいけば得られるため、特断の不便はあまり感じていません」
解散して1年目の今は、「ゆっくりと歩みながら、今後をふまえいろいろなことを模索している状態です」という石曾根氏。
地域との連携が、今後の課題
今後の課題は、地域との連携だ。
「PTA解散について、地域の方々からは100%の理解を得られているとは言い切れない状況です。とくに、歴代PTA会長を経験された方々からは、『自分の時代はこうだったのに、なぜこうなったのか』という疑問や反発の声が聞かれることもあります。
コミュニティ・スクールがうまく機能してない現状をふまえ、今後は地域の方々と共に学校が抱える諸問題を共有しながら、子どもたちや学校をどのように支援していけばよいのかを探っていきたいと思います。組織の立て直しには、ある程度の時間がかかります。最適解をすぐに出そうと焦らず、私が代表を退いたあとの体制も含め、長期的な視点で関わっていきたいですね」
明善小PTAの解散が知られるようになり、周辺の学校から問い合わせが増えているという。
「会員の負担感や役員・委員のなり手不足など、抱えている問題は、どのPTAも共通しているように感じます」と、石曾根氏は言う。
少子高齢化や共働き家庭の増加など、社会環境の変化は著しい。従来型のPTA活動が時代に合わなくなっているという声も多く聞かれる。
巷では「PTA不要論」が根強くはびこり、こうした解散の動きも徐々に増えつつあるが、子どもたちの教育環境を維持するためには、学校と保護者との連携や、保護者による学校支援は不可欠だ。
しかし、その役割を果たすのは、必ずしも「PTA」という組織でなくてもよく、「その学校」「その地域」ならではの仕組みがあればよいということだろう。
今後は、「PTA」という枠にとらわれず、地域や学校の実情に合わせた多様な支援の形を模索していくコミュニティが増えていくのではないだろうか。
(注記のない写真:Ushico / PIXTA)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


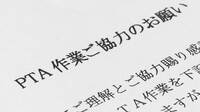





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら