「PTA解散」しても困らない?廃止した学校の変容、「選択と集中」が肝な訳 新制度構築や地域移行など新たな保護者組織
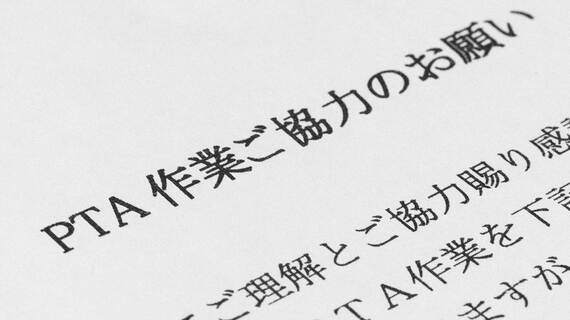
役員のなり手不足や教職員へのPTA業務依存が課題
2025年3月末。滋賀県立長浜養護学校(滋賀県長浜市)PTAが解散する。小学部・中学部・高等部からなる同校PTAの会員は323人(保護者207人、教職員116人:2025年2月現在)存在するが、役員のなり手不足や教職員へのPTA業務依存が長年の課題だった。
同校のPTA会長を務める藤居貴之氏は、こう話す。

2021年〜2022年度長浜養護学校PTA副会長を経て、2024年度同校PTA会長
(写真:本人提供)
「本校のPTA組織は、いわゆる従来型。本部役員会の下に4つの部会がありますが、本部役員の立候補者はほとんどおらず、最終的に教職員が保護者に依頼し一部の人だけに責任と負担が生じている状況が続いていました。また、本来PTA活動は、P(保護者)とT(教職員)が連携して行うものですが、本校においては、案内文書の作成や広報誌の制作など多くの活動を教職員会員が担っています。地域の慣例的な側面があるにせよ、児童生徒と向き合う時間がPTA業務にあてられてしまっている状況をどうにかしたいと。
さらに、共働き世帯の増加、特別支援学校で子どもの通院やリハビリなどが必要な家庭が多いことによるPTA活動参加へのハードルの高さも課題でした。これらをふまえ、2024年5月、本部役員会(会長、副会長、教職員担当者、管理職)を『長浜養護学校PTAあり方検討委員会』と位置づけ、今後のPTAのあり方について1年かけて検討することを提案しました」
PTA総会においても検討を進めることが承認され、同年6月から10月、会員に対しPTA意識調査アンケート、PTA活動にかかる時間実態調査を行ったのに加えPTA会員座談会や個別説明会を開催し、広く意見を聞く機会を設けた。
PTA意識調査アンケートの回答率は、約50%。「PTAは必要だと思うか」の問いに対して、「必要」と回答した保護者は16%、「不要」と回答した保護者は30%、「わからない」と回答した保護者は54%だったという。
「『不要』と回答する保護者が7、8割を占めると予想していたのですが、『わからない』と回答した保護者が半数以上いたことに、正直驚きました」と、藤居氏は言う。
「『わからない』という意思表示は『(PTAは)あってもなくてもいい』ということであり、その根底に流れるのは『PTAの存在や活動への無関心』といえると思います。ただ、この無関心は、会員に非があるのではなく、一部の人間だけで物事を決めざるをえないこれまでの体制によってもたらされたもの。
結果的にトップダウン的な運営になり、言いたいことがあっても言う場所や機会がなかったことが起因となっているととらえています。また、『PTAの目的は、学校のお手伝いや奉仕作業を行うこと』と思い込んでいる会員が少なくない傾向もみてとれました」(藤居氏、以下同じ)
全サポーターが運営に関わることができる「開かれた組織」に
調査結果や議論の内容をふまえ、現状のPTAのあり方での継続は困難と判断。必要な活動は残すことを前提とし、残った課題を解消する手段として、
① 2024年度でPTAを解散し、2025年度から新たな仕組みをつくる
② PTAを存続し、委員の削減やデジタル化を図る
2つの方向性について検討した。その結果、①の方向性が「必要な活動を残しつつ、なり手不足や過度な負担の解消及び軽減につながる」と裁定。2024年11月に臨時総会を開催し、2024年度でPTAを解散し、2025年度から新たな仕組みをつくりリスタートすることが決定した。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら