
だからなのか、僕が小学生の頃はPTAの委員は大体父親がやっていました。僕の父親もPTAの委員をやっていました。時々、親たちがわが家に集まって熱のこもった議論をしていました。保護者が教師の言動をとがめて学校に怒鳴り込んでゆくようなこともありましたし。当時のPTAってすごく熱かったんです。
でも、そのうちに軍国主義的な言動をするような先生もいなくなり、親が教師を監視する必要もなくなった。そこからPTAの変質が始まったのかもしれません。
その後は、1960年代からは、お母さんたちが先生と仲良くして、いろいろな学校行事をお手伝いして、学校を和やかにしてゆくことがPTAの主務という時代になった。でも、今はもうお母さんも専業主婦の割合が減って、働いている人が増えましたから、学校行事を手伝うような暇はないということになったのではないでしょうか。
――PTAは縮小傾向という学校もあるのですが、世の中のお節介も縮小されてもいいのでしょうか?
そうですね、でも、どんな集団でも、一定数のお節介な人は必要だと思うんですよ。全員がお節介になる必要はありませんが、一定数は要る。昔からお節介なおじさん、おばさんというのは必ずいたわけですよ。
全体の15%くらい、大人7人に1人くらいの割合でお節介な人がいた。「早く結婚しなさいよ」とか「子どもはまだなの?」とか「仕事はうまくいってるの?」とか、よけいなことを訊いた。
お節介は「一定数」必要
もちろん多くの人は、そういうのを「余計なお世話だ」と思って聞いていました。だから、周りの全員がお節介だったら、ほんとうに迷惑だと思うのです。でも、一定数は必要だと思うんです。お節介な人は差し出がましいことを言いますけれど、言った責任はとってくれる。見合いの相手を探してきたり、仕事を紹介してくれたりする。
こういう議論をするときは、どうしても「善いか悪いか」の議論になるのですけれど、これは「善し悪しの問題」ではなく、「程度の問題」なんです。ゼロか100かという話じゃなくて、さじ加減の問題だと思うんですよ。お節介な人はいすぎても困るし、いなくても困る。

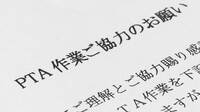





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら