
松下幸之助は、経営哲学というものを構築しただけではない。松下を論じる多くの学者、研究者、評論家が、松下を経営者のみから、見ているのは、象の一部をなでているようなもので、私からすれば、到底、それでは、「松下幸之助」の全体像を描きだすことはできないと思っている。確かに、経営者であったが、同時に、思想家、哲学者であった。
アメリカでの松下の人物像
実際、1964年、アメリカの『ライフ』誌は、日本特集を組み、そのなかで、“MEET Mr.MATSUSHITA”と題する記事を掲載しているが、松下を「最高の産業人、最高所得者、思想家、雑誌発行者、ベストセラー著者と5つの顔を持つ」と紹介している。この指摘の中で、アメリカ人が、松下を「思想家」として注目しているにもかかわらず、日本人が、とりわけ、学者、研究者、評論家が、「最高の産業人」すなわち、「経営者」としか認識しないのは、不思議というより、研究不十分、理解不十分の結果であろうと思う。
昭和46年6月の終わり頃、松下と京都の私邸、真々庵で、縁側に立って庭を眺めていると、「江口君、来月から、人間観の勉強をしようか」と、フッと言う。「わかりました」ということで、二人だけの勉強会が始まった。原稿は、もう20数年前から推敲に推敲を重ねたものがある。その原稿のコピーを、私が声に出して読み、それを松下も原稿の文字を目で追いながら、という、そして、ところどころで、松下が、「ここはこういうように書きかえてくれ」、「ここは、こういうことを言いたいが、それがうまく記述されていない」、「ここは、君は、どう思うか」というやり取りの作業が、実に、6カ月、休みなく、毎日続けられた。


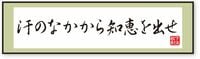
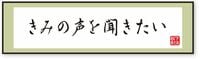
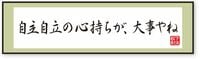




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら