一方でナルミさんが子どものころには、発達障害を持つ子どもの早期発見や専門的な支援はそれなりに進んでいたはずだ。発見が早いほど発達障害の特性によるトラブルや、それに伴ううつやひきこもり、自傷行為といった二次障害の予防につながるといわれる。
実際のところ、ナルミさんは「小さなころから普通とは違う子どもだった」。起床してから出かけるまでに2時間以上かかるのはざら。小学校に通う途中で見つけたシロツメクサとアカツメクサの違いが気になって何時間も道端に座り続けたり、何かに集中すると授業中に名前を呼ばれても気が付かないこともあったりした。
しかしながら学校の成績はトップクラス。ノートも取らないし、宿題も提出しないので教師との折り合いは悪かったものの、黒板に書かれていることや教科書を読めば、授業の内容を理解することはたやすかったという。「逆に先生の話は、聞いているうちに『なんの話だっけ?』となってしまいます。耳から入ってくる情報を処理することが苦手でした」。
父が単身赴任で、子育ては母任せだった
明らかに「普通とは違う子」はなぜ支援の対象から漏れてしまったのか。
ナルミさんは「うちはずっと父が単身赴任で、子育ては母任せでした。母にしてみると、僕に障害があるとは思いたくなかった。僕が普通とは違うことを認める勇気がなかったのではないかと思います」と振り返る。
発達障害がわかるパターンとしては、保育園や幼稚園などの先生から医療機関や療育機関に相談するように言われたことがきっかけだったという事例は多い。とはいえ、ここで両親から拒絶されてはお手上げだ。
ナルミさんは「障害を認めたくない」両親からよく折檻を受けた。しかし、ナルミさんにはなぜ叱られたのかという記憶がほとんどないのだという。学校の授業と同じで、途中からなぜ怒られているのかということを理解できなくなるのだ。結局覚えているのは、たまに帰ってくる父親から顔がはれるまで殴られたことや、母親から本やおもちゃを投げつけられたことだけ。
「育てづらい子どもではあったのでしょう。でも、僕の中では『叩かれて痛い思いをした』という記憶しか残っていない。もっと早く障害がわかっていれば、あそこまで叩かれることはなかったのではないかと思います」
実はナルミさんは高校生のときに自分は発達障害なのではと思い、医療機関を受診したことがある。このときは問診だけだったものの、すぐに広汎性発達障害(当時)と診断された。ただこのときも母親から「お前は自分で自分のことを病気にしている」「甘えているだけ」と言われ、わずか数カ月で通院と服薬をやめてしまったのだという。



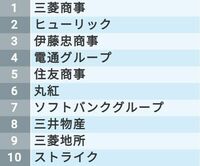





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら