スポーツの聖地、国立競技場の最後の日 父と息子の半世紀の物語

日本復興のシンボル
今から思えば、1964年は、戦後日本の復興を象徴する特別な年だった。
首都高速道路をはじめとするインフラが整い、この年の前後から、都心はその表情を大きく変えつつあった。とりわけ10月1日に開業した東海道新幹線と10月10日から始まった東京オリンピックは、日本復興のシンボルだった。
そして、その東京オリンピックの「顔」こそが「国立霞ヶ丘競技場」だったのだ。
1958年に竣工した国立競技場は、東京オリンピックを控え、バックスタンドを中心に大幅に拡張し、生まれ変わった。言ってみれば、このときから、スポーツの聖地としての役割を背負うことになったのである。
しかし、どんな物語も、始まれば終わる。
1964年10月10日、東京オリンピックと共に始まった国立競技場物語は、半世紀を経た今年、2014年5月31日、ついにエンディングを迎えることになったのだ。灯された聖火台の火は、この日、永遠に消えることとなった。
1964年10月10日、新生国立競技場では、東京オリンピックの開会式が行われていた。
約7万2000人の観客の目は、トラックを走る聖火リレー最終ランナーに注がれていた。ここまで、実に10万712人のランナーが手渡し続けてきたトーチを受け取るのは、この年、早稲田大学競走部に入ったばかりの坂井義則だった。
坂井は、1945年8月6日、広島市に原爆が投下された1時間半後に広島県三次市で生まれた。最終聖火ランナーに選ばれた理由のひとつは、その坂井が抱え持つ物語性にあったことは言うまでもない。

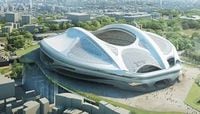































無料会員登録はこちら
ログインはこちら