
進行したがんや難病など、進行性の重い病気をもった患者さんへ余命告知をしたほうがよいかどうか、患者になったときに余命を聞きたいかどうか、議論されることがしばしばあります。
担当医に自分の余命を尋ね、「放置していれば、あと3カ月ですね」と返答されれば、患者やその家族は戸惑い慌てふためいてしまいます。平穏だった日常生活から、いきなり断崖絶壁に立たされていることに直面するのだから当たり前です。
人間には人生の重大な危機に対処する力が備わっています。しかし、この3カ月という期日を信じ込み振り回されてしまうと、呪文にかかったようにその力を失いしぼんでいきます。
訴えられた例もある
2017年8月の読売新聞の記事で『進行がん患者、聞きたいと思ってるのに 余命「告知なし」4割』と題して国立がん研究センター(東京都)と東病院(千葉県)で行われた研究結果が紹介されていました。

ここでは、「がん治療について余命を知りたいと思っていたが、医師から聞いていない人が、進行がん患者の4割に上る」と書かれていました。
しかし、実際には、「余命何カ月です」と断定的に言えるほど、医師は患者の余命を知っているわけではありません。
また、2018年10月には、同年1月に死亡した大分市の女性(当時57歳)に余命1カ月との診断結果を告知しなかったため、「残りの人生を家族で充実させることができなかった」として、遺族が女性の通院していた病院を運営する市医師会と主治医に対し損害賠償を求める訴訟を大分地裁に起こしたということが報じられました。ここにも、余命はわかるものとの前提があるように思われます。
2008年に報告されたアメリカの調査では、患者に具体的な余命について話す頻度は、「つねに」あるいは「通常は」と答えた医師は43%。「ときどき」、「まれに」あるいは「まったくない」の回答が53%であったと報告されています。
患者さんへの情報提供が進んだアメリカにおいても半々なのです。大分で起きた件も、余命を知らせなかったというよりは、病気の重症度や、死に至るのはどのような経過が可能性としてあるのか、などが十分に伝わっていなかったことが問題なのだろうと考えられます。



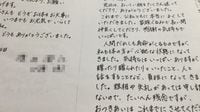






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら