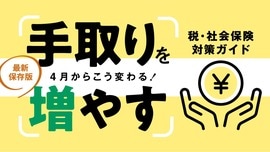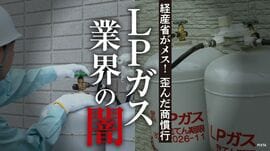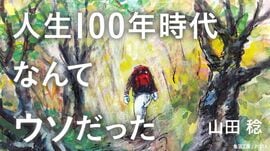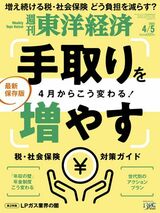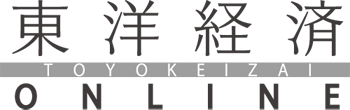「仕事を任せる上司」が部下の不評を買う理由 権限委譲にもバランス感覚が必要だ
もう1つ、こんな例があります。同じくメンバー育成に熱心なリーダーJさんは、とにかく自分の知識やノウハウをメンバーに伝えようと考えています。もちろん「権限委譲」が大切だと思っており、できるだけ多くのことをメンバーに任せようとしています。そのうえで、自分の経験をできるだけ多く伝えようと、メンバーを一生懸命に指導しています。
そんな中、あるメンバーから言われたのは「いつまでも細かく指示されて、仕事を任せてもらえない」という不満でした。能力が高い優秀なメンバーでしたが、「“任せた”と言っているのに、途中でいろいろ口出しをされたり、仕事を取り上げられてしまうことがある」と言い、そのせいでやる気がなくなってしまうことがあると言います。
そう言われると思い当たることがあるJさんが、このメンバーの指導であらためて心掛けたのは、「一方的に答えを言わない」ということでした。「質問を投げかける」「選択肢を示す」ということに徹し、そこから先はできるだけ本人に考えさせるようにしました。
はじめは本人に戸惑う様子があったものの、もともと積極性があるメンバーだったので、リーダーが関わり方を見直したことで、さらに自分から質問や相談をしてくる機会が増え、成長速度は高まっていきました。今はチームの中核メンバーとして活躍しています。
2つの例のどこが問題だったか?
この2つの例では、どちらのリーダーも「権限委譲」が大事だと考えており、それを実践しようとしていました。
しかし、メンバーはそれぞれ正反対の感情を持っていたという点が共通しています。前者では、リーダーは「余計な口は出さない」と思っていましたが、メンバーの気持ちは「放置されている」「仕事の押し付け」というものでした。一方で後者では、リーダーは「丁寧に教えている」つもりでしたが、メンバーはそれを「過剰な干渉」「やり方の押し付け」と思っていました。
ここで問題だったのは、それぞれの権限委譲の仕方が、リーダー自身の価値観や感覚によるもので、相手のレベルや感じ方に配慮していなかったことにあります。リーダーの多くは、自分の価値観と過去の経験によって、メンバーとの接し方が決まってきます。よかったこと、悪かったこと、反面教師のようなことも含め、自分がよかれと思うことを行動基準にします。
そして、私が見てきたリーダーの多くは、往々にして「メンバーに任せている」と言いますが、その任せ方は千差万別で、中にはとても任せているとは言えない関わり方をしている人もいます。自分の思い通りにいかないことにシビレを切らして、任せたことを取り上げてしまったり、途中でいろいろ口出しをして、メンバーがやる気をなくしてしまうこともあります。
しかし、リーダー自身はよかれと思ってやっているため、それをよく思わない人の気持ちになど気づきません。善悪の区別が明確なことであれば、自分の意識だけで判断すればいいのですが、それだけでは言い切れない、人によって感じ方が違うことの場合、自己判断だけでは足りません。また、メンバーは「自分も決定に関与した」と思うプロセスがあって、初めて「任された」ということを実感します。