
会社員は原則として、給与から必要経費を控除して税負担を減らすことはできない。しかし、「所得控除」と「税額控除」がある。所得控除は税率を掛ける前の課税所得から控除するもの。税額控除は所得税額から控除するものだ。
所得控除の代表は「配偶者控除」と「扶養控除」。2025年度税制改正の前まで、配偶者が給与所得のみで年収103万円を超えると合計所得金額が48万円を超え、配偶者控除が受けられなかった。
ただし、103万円を超えても133万円までであれば一定の金額を本人の所得から控除可能。配偶者控除の次の段階として「配偶者特別控除」という控除があるためだ。年末調整の際、配偶者の年収を勤務先へ正確に伝えないと損をする可能性がある。25年度税制改正で配偶者の年収の壁はもう少し引き上げられる見込み。詳細は今後決まるので、注目しておきたい。
また、大学生年代の子が年収103万円を超えてアルバイトをしても、今後は控除の対象となる見込み。年末調整時に、子の源泉徴収票も漏れなく確認しよう。
10万円超で使える「医療費控除」
配偶者控除や扶養控除は、会社が年末調整で対応してくれる。しかし、本人が確定申告することで税金を取り戻せるケースもある。例えば医療費が10万円超になった年に使える「医療費控除」だ。医療費控除は対象になるか判断に迷うことが多い。主なポイントを下表にまとめた。

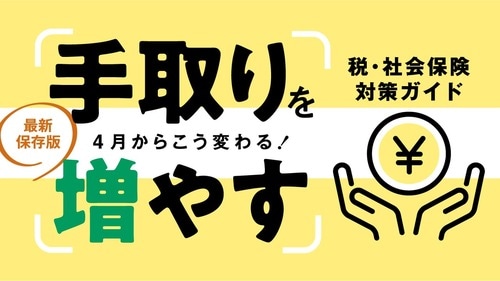































無料会員登録はこちら
ログインはこちら