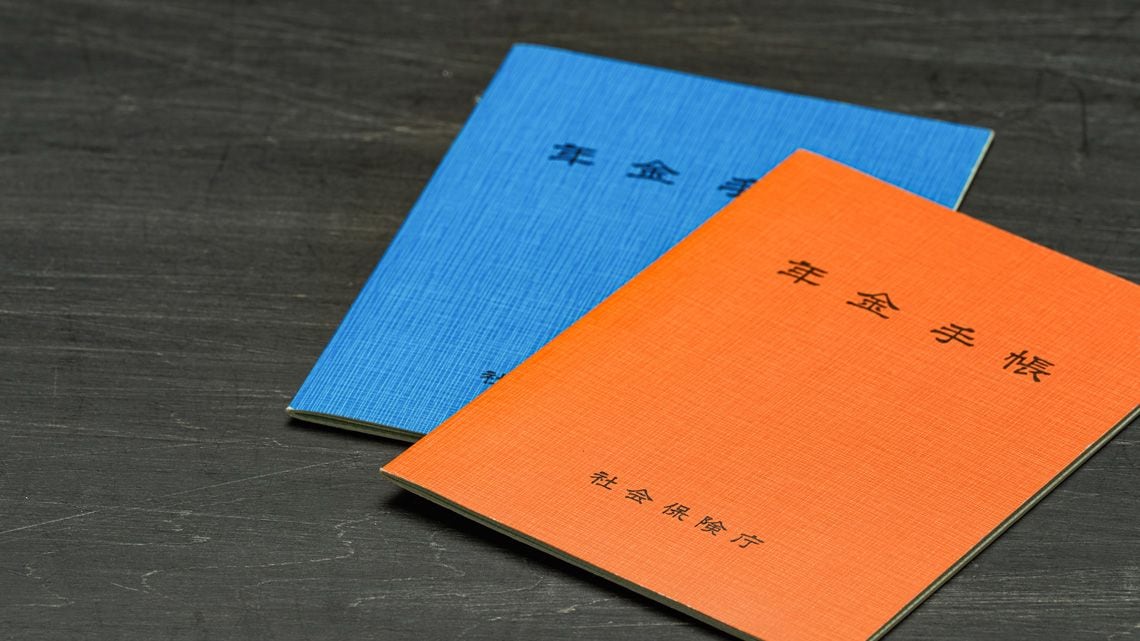
与党の調整が遅れ、年金制度改革法案の今国会での成立が見通せない。ただ、昨年末までの厚生労働省の審議会での議論で、大まかな方向性は見えている。関心が高いのは「在職老齢年金制度」の見直しだろう。
給与と厚生年金の合計が基準額(2024年度は月50万円)を超えると、超えた分の半額の厚生年金の支給が減らされる仕組みのことで、「50万円の壁」とも呼ばれている。
年金が減額されることについて、「過去に払った保険料に見合う給付が行われないのは社会保険の原則に反する」「就業調整の原因になる」「厚生年金の加入者のみが対象になるため就業形態を歪める」といった批判がある。
基準額は62万円程度へ引き上げ
厚生労働省の審議会では減額の廃止を求める意見もあった。だが最終的には、廃止ではなく、基準額を引き上げ、減額の対象者を減らすという案になった。
これにより、高齢就労者(厚生年金が適用される形で働きながら厚生年金を受給する人)のうち、減額される人の割合は、16%から10%へ減少する。現状50万円の基準額(給与+厚生年金)は、62万円程度へ引き上げられる。
廃止に至らなかったのは、「減額をやめると年金財政が悪化して将来の年金水準が低下する」「廃止の恩恵を受けるのは高齢就労者のうち2割弱の高所得者に限定される」といった声があったからだ。
そこで、基準額の引き上げを小規模にとどめるとともに、新たな2つの見直しもセットで盛り込まれた。

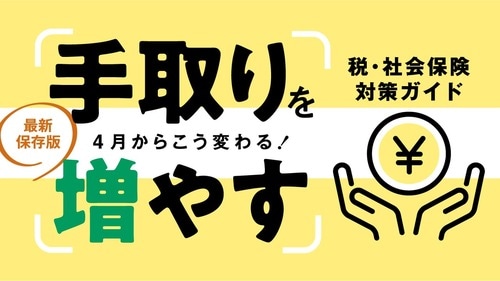
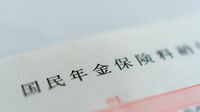































無料会員登録はこちら
ログインはこちら