<ライフスタイルの変化が年金の未来を明るくする>「モデル年金」ベースの議論はもうやめよう。本当の将来像を知れば、改革案は絞られる

昨年、2024年5月末の『週刊東洋経済』のコラムに「若年世代の年金受給はむしろ充実するという視点――報道で見落とされる世帯の形と働き方の変化」が書かれていた。
このコラムは、「専業主婦世帯と共働き世帯との割合は、1980年には64%、36%だったが、2023年には29%、71%と大逆転している」ことを示し、「こうした世帯の形や働き方の変化を加味して将来世代の年金給付水準を考えるとどうなるか」と問う。そして、「若年世代の年金受給はむしろ充実する」と結論づけていた。
この読みは、2024年7月3日に公表された公的年金保険の財政検証で証明されることになる。
明るい未来を描いた昨年夏の財政検証
2024年秋号の『読売クオータリー』での財政検証の解説記事のタイトルは「意外に明るい公的年金の未来図」だった。ほかにも、『共済新報』10月号には、「2024年財政検証で明らかになった公的年金の明るい将来像」というタイトルの文章もあった。
私も「『さらばモデル年金』誰も知らない財政検証の進化——女性活躍推進、子育て支援は重要な年金政策だ」を書き、明るい年金の未来を描いていた。2024年7月に公表された年金の健康診断である財政検証では、世間の通説とは異なり、将来の人たちのほうが今より年金額が高くなることが示されていたからである。
少子化が進んでいるのに、どうして年金が増えるのか。
この謎を考えていけば、長年にわたって多くの日本人に刷りこまれてきた「御神輿型」「騎馬戦型」「肩車型」でイメージする未来とは違う未来が現実であることがわかる。さらに厚生年金には入っておいたほうがよさそうであることも理解でき、未来についてはもっと楽な気分で生きていてもよいこともわかって、多くの日本人のウェルビーイング(心身と社会のよい状態)は随分と高まると思う。




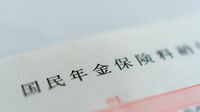




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら