<ライフスタイルの変化が年金の未来を明るくする>「モデル年金」ベースの議論はもうやめよう。本当の将来像を知れば、改革案は絞られる
2019年の参議院選挙の前に、「老後2000万円不足」の騒動があった。あのときは、年金以外に収入のない世帯は毎月5万4519円不足しているというデータに基づいて、平均余命を掛けた額2000万円が足りないという騒動が起こっていた。
しかし同じ資料には、「高齢夫婦無職世帯の平均純貯蓄額 2484万円」が書かれており、不足と言われた2000万円を上回っていた。ほとんどの人たちは、収入や貯蓄額に合わせて支出を調整して生活をしているわけだから、「老後2000万円不足問題」というのは、最初から問題もないところにみんなで大騒ぎした、ただの騒動にすぎなかった。
2000万円騒動後の「あおり営業」と規制の強化
騒動の結果として「つみたてNISA」の契約数が急増している。並行して、2000万円騒動をきっかけに、人々の不安を利用したあおり営業が多く出てきた。このあおり営業の動きに対して政策が動く。
金融庁は2021年9月に、保険商品を販売する際には公的保険を説明するようにする「監督指針の改正方針」、すなわち「公的保険を補完する民間保険の趣旨に鑑み、保険募集人等が公的保険制度について適切に理解をし、そのうえで、顧客に対して、公的保険制度等に関する適切な情報提供を行うことによって、顧客が自らの抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性を理解したうえでその意向に沿って保険契約の締結がなされることが図られているかという点などを監督上の着眼点として明確化する」方針を示した。
業界から大変な反発が起こったわけだが、それでも進めていって、2021年12月に監督指針は改正されている。
それを受けて2022年3月に金融庁のホームページに、公的保険制度を解説するポータルサイト「公的保険について――民間保険加入のご検討にあたって」を金融庁は厚労省と一緒に作って、民間保険などを販売する際にはこれを参考にして、売る人も買う人もみんなで勉強しましょうという状況になった。
その翌月2022年4月に厚労省は「公的年金シミュレーター」を公開し、今では、上述の金融庁のポータルサイト「公的保険について」で紹介されている。
公的年金とライフスタイルの密接な関係
「さらばモデル年金」には、「今回の財政検証は、女性活躍を推進することと、子ども子育て支援を充実させること、加えて、65歳以上の就労の機会を準備していくこと、そして安定した年金制度を構築していくことは、実は同じ方向を向いていることを明らかにしてくれました」と書いていた。
労働市場は今、これまでの需給が弛緩した市場から逼迫した市場へと変わり始め、労働力の希少性が高まっていく社会を迎えている。この労働力希少社会は、賃金をはじめとした労働条件の競り上げ競争が起こり、魅力的な職場を提供するように労働市場に働きかけ、人々のライフスタイルを変えていき、その変化は公的年金保険にはプラスの影響を与える。
労働市場が逼迫している労働力希少社会では、厚生年金が適用されていない企業で働いている人たちは、厚生年金が適用されている企業に移ることも容易となる。将来の低年金対策としては、厚生年金の非適用事業所から適用事業所への転職のすゝめはかなり有効となる。
ライフスタイルと労働市場が公的年金保険に有利に変化していく未来は、そう暗い話ばかりではないように見えるのだが。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




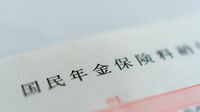


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら