
4月3日(木) マツダ社長が明かす「ライトアセット戦略」の勝算
4月18日(金) 「PBR0.3倍」マツダが株式市場で不安視される真因
4月23日(水) トランプ関税で問われる、マツダ「北米改革」の実力
4月中旬 「エンジンを諦めない」マツダ流、EV時代の勝ち筋
Coming Soon
――マツダは年間販売台数が100万台規模でありながら、日米欧アと手広くビジネスを行っています。バランスが取れていると言えますが、明確な強みが見えない点が株式市場からの低評価につながっているのではありませんか。各国市場をどう強化しますか。
もともとマツダが得意とするヨーロッパは今も安定している。電動化の進展はわれわれの想定より少し早かったが、中国の長安汽車と共同開発した新型バッテリーEV(電気自動車)の「MAZDA 6e」を今夏に導入することで対応していく。
北米市場は直近5年ほどで成長し堅実になっている。これはマツダにとってかつてなかったことだ。商品がよくなっただけでなく、市場自体に地力がついており、当社のビジネスに対して有利に働いている。ただし、これ以上アメリカに軸足を置くと、なにか課題が起きたときにバランスが崩れてしまう。
台数ありきは物事が絶対におかしくなる
――アメリカ市場のウェートを落とすという意図ですか。
いや、販売台数を増やすことにとらわれ過ぎないということだ。台数ありきでは物事が絶対におかしくなる。アメリカで年間40万台を売る力が付いた(2024年は42.4万台)。だからといって来年度に50万台を目指すかというと、そういうノリではない。
大事なのは、お客様に満足していただき、ロイヤルティーを上げてクオリティの高いビジネスにすることだ。そのほうが絶対に長続きする。
――トランプ政権はアメリカに輸入される自動車に25%の追加関税を課すことを決めました。アメリカで販売するマツダ車の大半は日本とメキシコから輸出された車です。関税の影響や対策は。
これについては、まったくわからない。関税がどれくらいのものになるのか、どれくらい続くのか、それによって北米の中がどうなるのかも全然わからない。なので、対策はいろいろとあるが、実際に何をいつどうするかは決められない。最悪のケースを想定しながら考えている。
――アメリカでの生産拠点として、トヨタ自動車と合弁で運営するアラバマ工場があります。現地生産を拡大することを考えていますか。
昨年、アラバマ工場では約10万台を製造した。生産能力は年間15万台あるので、アウトプットを1.5倍に拡大することは自分たちでできるし、やればいいと思う。その次の手に関しては考えないといけない。












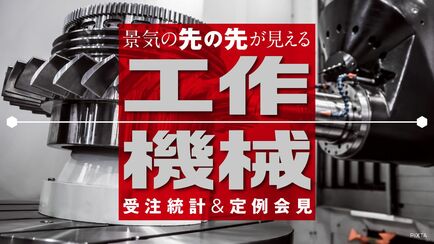























無料会員登録はこちら
ログインはこちら