無用の悲劇を止める方法、終戦は早められるのか?
さて、終戦の時期が遅れることには、敗戦国、とりわけ戦争責任者が受けるであろう処罰、つまり、彼らが予想する自身にとっての多大な損失発生の影響も大きい。
もし、なんらかの方法で、敗戦国の責任者に対する罰を軽減すること、あるいは戦争のさらなる継続によって罰がより厳しくなることを、戦勝国側が信憑性のある形で約束できれば、決定の権限を持つ者が敗戦を先送りするインセンティブは減らせる。
しかし、こうした解決策の実行には困難が立ちはだかる。まず後者の「厳罰化」について、個人への罰としては、死刑以上の選択肢がないという制約が問題になる。すでに自らの死を覚悟した敗戦の将には、(「本人のみ」を対象とする限りにおいて)どんな脅しをチラつかせたところで、追加的な効果は期待できない。
では、前者の「処罰減免」はどうか。こちらは少なくとも二つの問題を抱えている。一つは国内政治的な問題、戦勝国側の国民感情の壁だ。最終的に勝利を収めるとしても、その過程では戦勝国も大きな犠牲を払っているだろう。終戦を早めるためとはいえ、自国民を多く殺害した敵国の将を厚遇するなど、なかなか世論が許さないのではないだろうか。
二つ目の問題は、新たに戦争を引き起こすインセンティブに関連する。もしも大規模な戦争を引き起こして負けたときに、当事者としてその責任を深く追及されないのであれば、そもそも戦争を仕掛けやすくなってしまう危険があるのだ。
いったん戦争が起こってしまった後、事後的には、早期の終戦を促すため、責任者への処罰を減免することが望ましい。しかし戦争が起こる前、事前には、できるだけ厳罰を設定しておくことがベストになる。
勝敗がはっきりと決まる事柄をめぐる制度設計は、言うまでもなく難しい。ただ、戦争の例で述べた、敗者の側のみが終結を先送りにしようとすることや、事前と事後のインセンティブの違いを考慮に入れることで、より建設的な議論ができるのではないだろうか。
【初出:2013.8.17「週刊東洋経済(マンション大規模修繕)」】
(担当者通信欄)
記事にある、「先送り」にはそれで良いケース、良くないケースどちらもあるということ。何かコトが起こるにしても、前と後では受け止め方、対処方法が変わるということ。そんな当たり前のようで見落としがちな話を改めて認識することで、日々の仕事から、しばしば問題となる領土のこと、いざ何かコトが起こってしまったときの現実的な対応までを、冷静に考えるためのヒントが得られるのではないでしょうか。
さて、安田洋祐先生の「インセンティブの作法」最新記事は2013年9月9日(月)発売の「週刊東洋経済(特集は、新成長ビジネス100)」に掲載です!
【今日で世界が終わるなら、僕らに何ができるだろう】
一年にわたる連載も今回が最終回です!「もしも今日で世界が終わってしまうとしたら、何をしたいですか?」そんな問いにああでもないこうでもないと話し込んだことが多くの方にあるのではないでしょうか。最後の大散財!なんて答えは定番かもしれませんが、記事では、それが実は不可能であることを解き明かします!
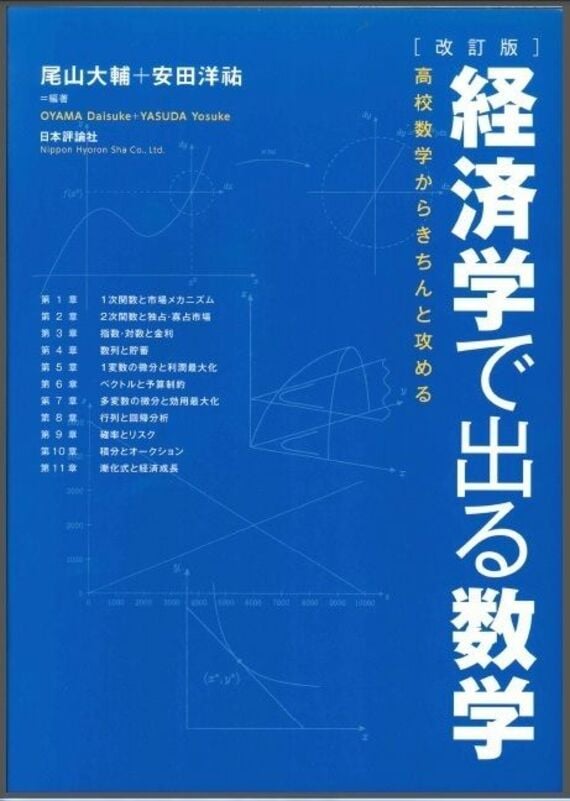
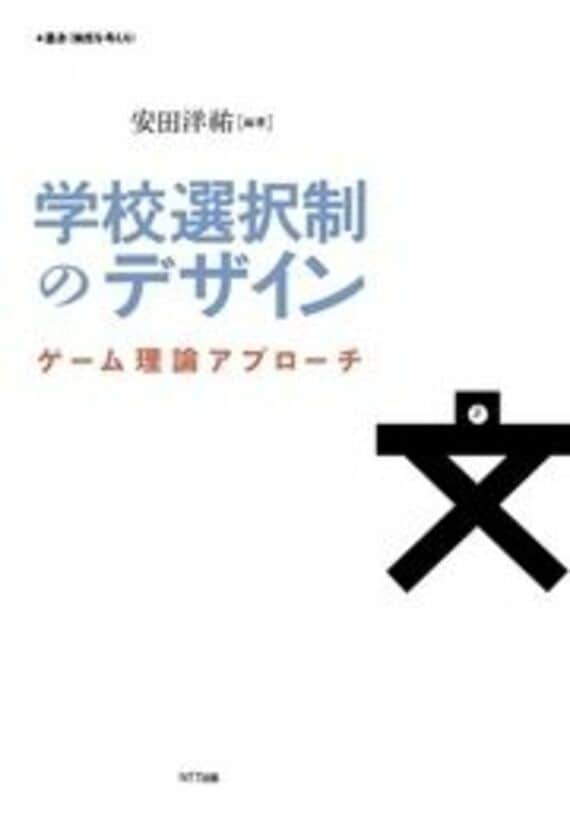
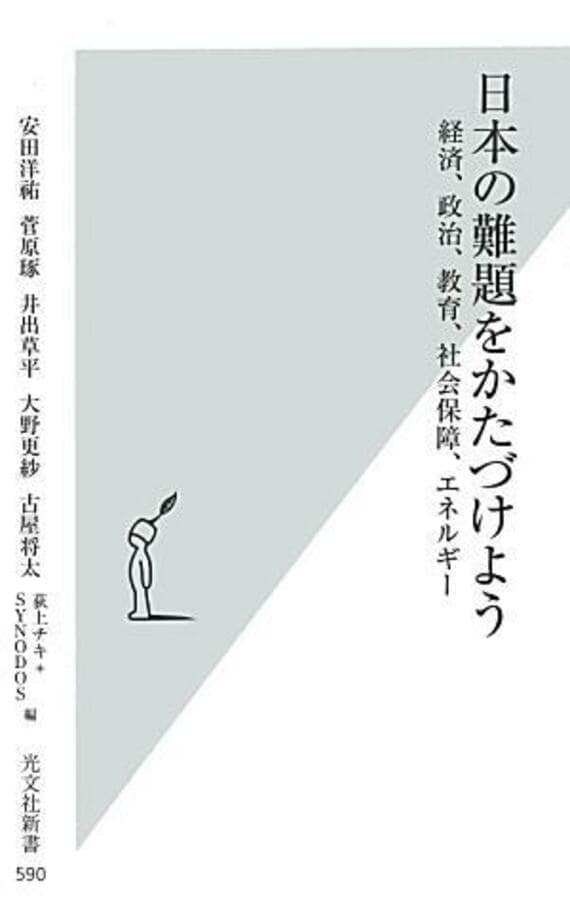
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら