脱藩官僚が育む「平成龍馬」の夢 新世代リーダー 朝比奈 一郎 青山社中株式会社 筆頭代表
――迷った末に選ばれた通産省。入省してどんなお仕事にしましたか?
入った直後はODA関連の部署で働きました。97年にアジア経済危機が起きて、日本として何かできることをしたい。そういう場面で「特別円借款」という制度を作ることになった。どういうシステムかというと、日本がおカネを出すけど、だが、そのおカネを使う仕事は日本企業が受注しようという仕組みのものです。
「他省の言うことももっとも!」と思っても背中に銃口が…
ただこの円借款のルールについては大蔵省、通産省、外務省などの意見をまとめて決めることになっていて、難航を極めました。大蔵省は当時「新宮澤構想」というものを出したところで、今回の件にはあまりおカネを出したくないというスタンス。片や、外務省は70年代に評判が悪かった「ひも付き援助」のニュアンスを極力出したくない。
一方の通産省はといえば、当時「顔の見える援助」が大事と言われ始めていたこともあって、日本にもメリットがあることを打ち出したい。三者とも正論だけど、バラバラの考えを持っていました。
こうした議論を通じて行政の“縦割り”というものを痛感しました。仮に通産省の僕が「なるほど、外務省の言うとおりだな」と思っても、「通産省の立場」を考えると意見を変えることができない。後ろから銃口を突きつけられているようなものです(笑)。

それじゃあどうやって結論を出すのかというと、発表文書の文言の調整を行うんですね。ただ全部の意見を無理やり混ぜ込むので、何だか訳のわからない玉虫色のものが出来上がる。「今回はこれで行く」と決める司令塔組織がないのが致命的な欠点です。
その後に行った特許庁でも同じようなもどかしさを感じた。当時アメリカではビジネスモデルや遺伝子配列に関する発見まで、ガンガン特許が出されるようになっていて。日本もこれから製造業だけじゃ新興国に勝てそうにないし、知的財産権をしっかり確保していかなければ、という流れができていた。
そこで総務省に人員増強のお願いに行くんだけど、5人くらいの審査官の増員がやっと。その間にアメリカでは500人増やしているんです。日本の仕組みではそれはできないな、とつくづく感じました。
政策作りでは、日本とアメリカじゃ勝負にならない
――この頃からだんだん、霞が関改革に対する思いが芽生えてきたんですね。
決定的なきっかけは留学したこと。2001年からアメリカのケネディスクールという、各国の行政官も来ている場に身を置く機会を得ました。アメリカの政策の作り方を見ていると、圧倒的に専門家が多い。
日本では、例えば、安全保障の政策担当者が「僕はジョセフ・ナイに教わった」と豪語していたりするけど、アメリカではそのナイ氏をはじめ本物の専門家が省の幹部として担当者にもなる。先生と生徒じゃ勝負にならないですよね。
考えてみれば、自分のいた経産省にも経済学の博士号を持っている人は数えるほどしかいないし、起業経験者など現場の経験が豊富な人もいない。そもそもそういう人が入れる採用の仕方をしていない。曲がり角に来ている日本でこの状態でいいのか? と疑問を持つようになりました。


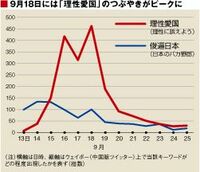






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら