クマ問題に絡めて写真配置…宇多田ヒカルさん「本人の私でも騙されそうになったわ」。読者をミスリードに誘う《進化型コタツ記事》の脅威とは?
注意すべき危険信号として、扇情的な見出し、情報源の不明確さ、一次情報と二次情報の混同がある。「~らしい」「~とのこと」など伝聞形式、根拠となる情報が消えている、匿名アカウントからの情報は要注意だ。
表やグラフの悪用、感情に訴える要素、繰り返しによる真実錯覚効果にも警戒が必要だ。同じ情報に繰り返し接触すると真実と錯覚する傾向があり、拡散の多さは真実性を保証しない。
日本のファクトチェック機関として、17年発足のFIJ(ファクトチェック・イニシアティブ・ジャパン)がガイドライン作成とClaimMonitor(疑わしい情報のデータベース)を提供している。
22年発足の日本ファクトチェックセンター(JFC)はIFCN認証を得た日本初の団体で、「正確」「ほぼ正確」「根拠不明」「不正確」「誤り」の5段階判定で200本以上の記事を公開している。JFCファクトチェック講座は無料で公開され、実践的な検証方法とツールの使い方を詳細に解説している。
誰もが「騙される」可能性を認識するべき
今後、コタツ記事を量産するAIが進化していくと予想しているが、それ以上に、SNSを通じた情報伝達が偏った記事に触れる機会を増やしていることが、より大きな問題になり得ると考える。
SNSをはじめとする情報プラットフォームは、AIを駆使したアルゴリズムで、ユーザーの満足度を高めている。しかし、それが結果的にコタツ記事問題を深めている側面もある。
例えばTikTokの研究では、特定の政党や選挙活動などへの不信動画を20本視聴するだけで、アルゴリズムが極右過激主義やQAnon陰謀論を多く見せるようAIがトレーニングされたという。
こうした現象をフィルターバブルといい、SNSがアルゴリズムによってコンテンツの閲覧数を最大化しようとすると、思想の分極化や誤情報拡散、フェイクニュースの増加・増幅といった現象が起きることが、22年にネイチャー誌で発表された。
日本では、“他人に不快感や迷惑をかけるべきではない”という規範が、オンライン行動での同調圧力を強め、また意見を述べる際に多くのユーザーが匿名性を重視する。この傾向が、フィルターバブルの呪縛を強めることは意識しておくべきだろう。
発信メディアのレベルでは、コタツ記事の抑制と取材に基づく質の高いジャーナリズムへの回帰、収益モデルの見直しが必要だろう。すでに多くのビジネス系メディアがサイトの有料化に舵を切っている。
社会レベルでは、デジタルリテラシー教育の推進、ファクトチェック機関の育成・支援、プラットフォーム規制の検討が急務だろう。国家レベルでの取り組みも必要な状況だ。
そして重要なことは、誰もが騙される可能性を認識することだ。
教育レベルや専門知識があっても認知バイアスの影響を受ける。「自分は大丈夫」と自信を持っている人ほど、認知バイアスの影響は強い。寛容性を持ち、異なる意見も受け入れる余地を持ち、情報は「正しい・間違い」の二択ではなくグラデーションがあると理解するべきである。
宇多田ヒカルさんはXで「ネットや週刊誌の情報鵜呑みにしてるのは情報に弱い少数派が目立ってるだけだと信じてるけど」と綴っている。
残念ながら現時点で、少数派とは言い切れない状況がある。しかし、「本人でも騙される」構造的問題は、私たち全員が直面している課題。解決するためには、まず現在の情報環境がどのようになっているか、頭の中を刷新するところから始めるべきだろう。


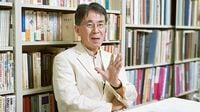




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら