クマ問題に絡めて写真配置…宇多田ヒカルさん「本人の私でも騙されそうになったわ」。読者をミスリードに誘う《進化型コタツ記事》の脅威とは?
PNAS(米国科学アカデミー)が21年に発表した研究では、Facebook、Twitter、Reddit、Gabから1億件以上のコンテンツを分析し、FacebookとTwitterではユーザーのホモフィリック(同質的)なクラスター化が進みやすいことが示されていた。
つまり、同じ考えの人が集まりやすい、ということで、これは他のSNSにも見られるものだ。その結果、エコーチェンバー効果が、極めて強く表れる。
エコーチェンバー効果とは、自分と似た意見を持つ人々が集まる発言空間で繰り返しコミュニケーションすることで、その中で話されている意見が一般的にも正しいと信じ込むというものだ。
人は同じ意見を持つ人と親近感を覚え、自分の考えが強化されることで、強い同調力を伝えたい相手に求めるようになる。また、SNSのアルゴリズムも「いいね」「シェア」「コメント」に基づいてパーソナライズされているため、フォローしていない第三者の意見もタイムラインに流入し、同じ考えの人とのつながりが広がる。
Science誌が18年に行った大規模な調査では、06年から17年にTwitterで拡散した12万6000件のニュースを分析すると、虚偽情報は真実より70%速く拡散し、特に怒り・不安・驚きなどの強い感情を伴うコンテンツが最も拡散しやすかった。
また、Harvard Kennedy Schoolによる20年の研究では、新型コロナの流行に行き場のない怒りを感じている人が、COVID-19に関する虚偽の情報や主張を「科学的に信頼できる」と判断し拡散する傾向が強いことも判明している。
真偽を見極めるために“今すぐできること”
では、騙されないためには、どんな心構えが必要なのだろう?ファクトチェックの基本手順は3要素からなる。
第三者が確認できる証拠の調査・明示、そして真偽・正確性についての判定だ。もっとも重要なことは、“事実と意見の区別”だ。意見として発言している内容を、事実として口伝する例は多い。個人の価値観に基づく「意見」は、事実ではないのだ。
例えば新型コロナウイルス関連では、コタツ記事で”○○病院の医師”などの引用が繰り返されたが、医師免許を持っていることと、公衆衛生のノウハウを有す専門性を有していることは異なり、情報が完全ではない中では専門家でも判断を誤る。
また情報源の信頼性評価で、一次情報を優先することも重要だ。政府、自治体、国際機関、学術機関の公的情報を最優先とし、複数の異なるソースがある場合は、よりそれらの情報ソースが何をもって情報を確認しているかを辿り、一次情報であるかを確認する。
国や自治体が嘘をついている、といった意見は、最初に無視するべきだ(誤った情報、異なる意見ならばあるだろうが“嘘”という強い言葉は、発言者の弱みを示していることが多い)。
画像・動画の真偽確認では、Googleレンズ、TinEye、InVID-WeVerify toolkitなどのツールを活用し、オリジナルを探し出してみるといい。過去の災害画像が現在のものとして使われているケースもあるが、最近であれば過去画像をもとにAI生成している場合もある。


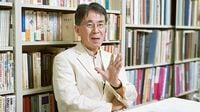




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら