クマ問題に絡めて写真配置…宇多田ヒカルさん「本人の私でも騙されそうになったわ」。読者をミスリードに誘う《進化型コタツ記事》の脅威とは?
穏当に言うならば、昔からいる文献派の筆者とも言える。取材が難しい相手の場合もあり、また製品レビューなどではあえてメーカーなどに黙って評価することが良いケースもあるかもしれない。
しかし、だからと言って取材を省略できると元記者が断言していることに違和感を覚えた。情報の元、ニュースの元を作っているのは人間だ。その人間、一次情報にアクセスする試みを行わずに得られる情報は、はるかに少ない。
そのころの筆者は、「HD-DVD対Blu-ray」の企業間戦争で、両方の当事者に毎日のように会っていたこともあり、報道と現場担当者、開発責任者、経営者、そして企業ごとの立場によって、見えている景色が大きく異なることを感じていた。そのこともあり、私は揶揄の意味も込めて「コタツ記事」と表現した。
12年にこの言葉がネット上で一気に広まったが、その後、コタツ記事は悪質化の一途を辿った。
根本の原因は、ネット記事の報酬体系にある。記事を掲載するウェブサイトの収益は、有料サイトを除きほとんどが広告に依存している。そしてそうした広告の多くは、記事の品質ではなく、「何回、どんな属性の人に、どのぐらいの時間滞在して閲覧されたのか」などの情報をもとに配信されている。
「誰が、どのような品質で、どれほどの手間をかけて書いたのか」といったことはほとんど考慮されない。つまり、記事生産のコストが低いほど収益性は高い。報酬システムとして、品質を評価するための仕組みが(個々の編集者と筆者の間などは別として)確立していないのだ。
コタツ記事の15年史
当初「文献派」として中立的に捉えることもできたコタツ記事だが、段階的に悪質化した。
初期(10年前後)はテクノロジー系ニュースをネット情報で総合評論する程度だったが、中期(15-16年)には、記事を論評するキュレーションメディアが台頭し、決定的事件が起きる。DeNAのWELQ問題だ。
医療情報サイトWELQは、クラウドソーシングで専門性を有しない筆者を低額で集め、ネットで調べた内容をコピペで再選する記事を量産した。「肩こりは幽霊が原因」といった医学的根拠のない情報を掲載し、SEO対策で検索上位を独占したが、16年12月に閉鎖に追い込まれた。
20年以降は、こうした記事作成の手法がフェイクニュース拡散装置へと進化した。コロナ禍で対面取材が困難になり、スポーツ紙のWeb版がコタツ記事の大量掲載を始めたためだ。
22年には中日スポーツがロシアのウクライナ侵攻関連でプロパガンダを拡散し、24年には毎日新聞までもが外注でコタツ記事を掲載。なりすましアカウントの発信を見抜けず、記事で引用してしまい誤報を流した。


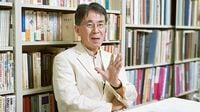




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら