窪田:子どもたちが自分の生き方を見つけて変わっていく実例も多くご覧になっていると思いますが、印象的なエピソードはありますか?
白井:長く引きこもっていた子どもが、毎日朝5時に自発的に外出できるようになった例もありました。きっかけになったのはスマートフォン向けゲーム「ポケモン GO」です。この子は本当にずっと家から出ていなかったので、靴もサイズアウトしていて足に合うものがなかったのです。しかし、わざわざ今の自分に合った靴を購入して外出するようになったのですから驚きました。
窪田:子どもが家の中に引きこもってしまうのは、目のためにもよくありません。私も眼科医として「1日2時間は外にいてほしい」と発信していますが、ポケモン GOが外出の理由になったのですね。
「足りないこと」ではなく「できたこと」に目を向けて
白井:ここで重要なのは、その子どもが靴を買ったり外に出たりしたことを、まずはきちんと認めてあげることです。
子どもが変わり始めても、親はつい「ゲームしかしていない」とか「いつ学校に行けるのか」とか、足りないことに目を向けてしまうんです。不登校や引きこもりの子どもはとくに自己肯定感が下がっているので、こうしたマイナスの言葉には非常に敏感です。大人にとっては小さな一歩に見えても、子どもにとってはものすごく頑張った大きな一歩なのです。
窪田:親も焦っているから、ついその先を見てしまうのでしょう。せっかくの頑張りを最善策ではないように言われたらがっかりしてしまいますね。
白井:教育現場だけでなく企業で講演することも多いのですが、そんなときには、日本の大人が学校の中のことをあまりにも知らないと訴えています。通知表を見ているだけでは、わが子のことも、わが子を取り巻く環境のこともわかりません。ただ学校教育を批判するだけでなく、一人ひとりが子どもの教育に関心を持ち、未来を担う子どもたちと自分なりにどう関わっていくかを考えて選ぶことで、大人も――ひいては社会もよい方向に変わっていけるのではないでしょうか。
(構成:鈴木絢子)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

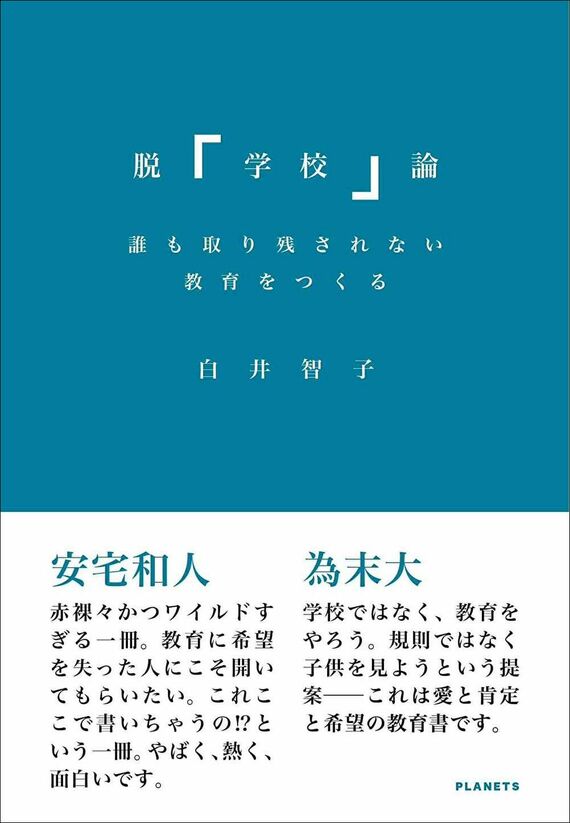
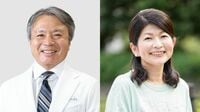





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら