現代の若者と同じように3人は悩み、葛藤しながらそれぞれの道を歩んでいきますが、沖縄に起こった激動の時代の大きな渦に巻き込まれていくことになります。
物語の舞台は、1952年から1970年にかけての沖縄「コザ」の町。「コザ」とは、現在の沖縄市中心部の「コザ十字路」から胡屋(ごや)・中の町エリアに広がる地域を指します。
1956年からは「コザ市」となり、1974年に現在の「沖縄市」に改称されるまでは、日本で唯一のカタカナ表記の行政地名として知られていました(現在は北海道の「ニセコ町」のみとなっています)。

映画で描かれる1952年の日本は、サンフランシスコ講和条約が発効されて主権が回復していたわけですが、当時人口が90万人ほどだった沖縄は、引き続きアメリカの施政権下に置かれることとなりました。
当時の沖縄は、車は右側通行、通貨は米ドルの「アメリカ」の世界。本土に行くにはパスポートが必要でした。
文化的にもアメリカの影響を大きく受けており、たとえば計量では現地で一般的な「ヤード・ポンド法」が採用され、そのため現在でも沖縄で販売される牛乳パックは、全国的な1リットルサイズではなく、946mL(1/4ガロン)が基本になっています。
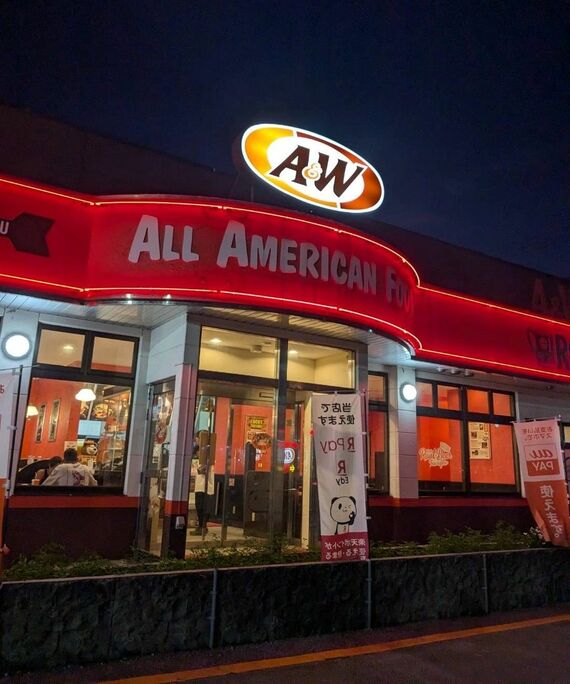
沖縄県内でも一、二を争う繁華街
また、この時代にアメリカから持ち込まれたランチョンミートなどの加工食品の影響で、ポーク玉子やチャンプルーの具材が一般的になり、現在の沖縄料理につながっているとも言われています(それまでの沖縄の食文化では、豚肉やヤギ肉が中心だったようです)。
このように、日本でありながら、日本の法律とは異なる独自の制度で統治されるその社会に矛盾が生じ、徐々に混乱していく様子は映画にも克明に描かれています。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら