生成AI導入で効率化しているのに"儲からない"のはなぜ? 意外と多い「自己満足の落とし穴」3つのパターン。「重要なのはAIそのものではない」
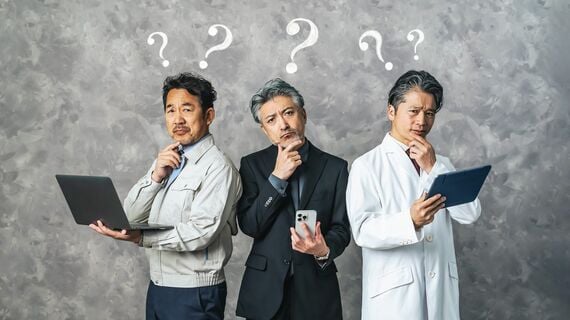
「なぜこれほどまでにAIを活用しているのに、業績がまったく上がらないんだ……」
ある大手製造業の営業部門を訪問したときのことだ。ChatGPTの勉強会を毎週開催し、生成AIによる業務効率化で年間表彰まで受けた部署である。
部長は誇らしげに「うちは全員がAIを使いこなしています」と胸を張った。しかし決算資料を見て愕然とする。売り上げは前年比マイナス2%、営業利益は20%近く低下していたのだ。
なぜ、こんなことが起こるのか? 今回は、生成AIを導入しても売り上げ・利益が上がらない原因と対策について解説する。AIによる効率化が自己満足に終わっている企業は、ぜひ最後まで読んでもらいたい。
「効率化」と「成果」を混同する危険性
先ほど紹介した会社の場合、問題の本質は単純だ。「効率化」と「成果」を混同しているのである。
メール作成が10分から3分になった。議事録作成が30分から5分になった。素晴らしい効率化だ。しかし、それで終わっている。
削減できた時間で何をしているのか。この質問に明確に答えられる企業は驚くほど少ない。
「いろいろな要因が重なっているんです」
「市場環境が厳しくて……」
「競合が値下げしてきたので」
営業部長はこう言い訳する。しかしこれらは昨年も一昨年も同じだったはずだ。AIを導入する前から存在した要因である。それなのに、なぜAI導入後も業績が変わらないのか。
答えは明白だ。効率化で生まれた時間を、売り上げにつながる活動に投資していないからである。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら