我が家の例ですと、子どもたちは日本の小学2年生と保育園の年中の時期にマレーシアに移住しました。
上の子は通信教育などで英語に触れる機会はありましたが、あくまで「触れる」程度。実質2人とも英語ゼロの状態でのスタートでした。
子どもたちのインター校には日本人の生徒も数人おり、最初は本当にありがたいことに彼らが学校生活をサポートしてくれました。
授業中は英語以外の言語を話すことを禁じているインター校が多いので、休み時間に慣れ親しんだ母国語で友達と話すことができる、という環境は、子どもたちの心の安定に一役買ってくれたようです。
インター校には「英語補講クラス」を設けている学校もあります。
その場合は生徒の英語レベルに応じて、通常の英語の授業を受けるか、補講クラスで初心者向けの英語の授業を受けるかが決まります。また、状況に応じて「英語集中クラス」に参加することもあるようです。
子どもたちのインター校の場合、「英語集中クラス」は通常のクラスとは時間割が大きく異なり、算数や体育など、一部の授業以外はすべて英語の授業になります。
同学年の他の生徒が受けている授業を受けないことになりますので、フォローアップが大変だという親御さんの声を聞いたことがあります。
インター校で「英語で学ぶ」ことの難しさとは
英語の伸びについては子どもたちの個性もありますから一概には言えませんが、2年半経ち、子どもたちの努力もあって、2人とも日常でのコミュニケーションはスムーズに行えるようになりました。
また、英語の抜き打ちテストでも6~7割は点数がとれるようになっています。そういう意味で、「英語はうまくなった」と言えるかもしれません。
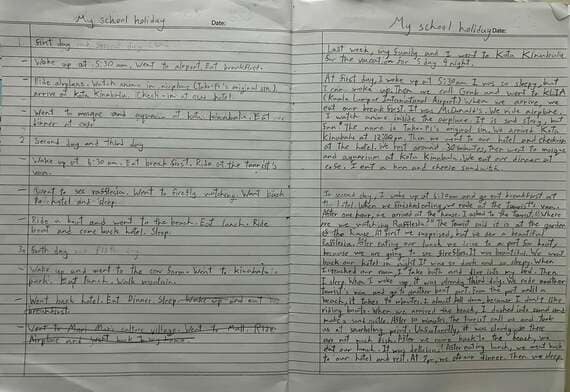
そのうえで、インター校は「英語を勉強する場所」ではなく「英語で勉強する場所」です。
日本の学年では小学5年生の上の子が、「サイエンスの内容がわからない」というので、試験に向けて一緒に内容を確認したときのことです。
「What is a variable in an experiment?(実験における変数とはなんですか)」
そもそも単語の意味がわからない。
そして、辞書を引いて単語の意味がわかったら、次にその単語が意味する内容を理解する必要があります。
母国語でも難しいことを、英語という慣れない言語で行うわけですから、宿題ひとつとっても時間がかかりますし、サポートがないと何から手をつければいいかわからない場合もあります。
改めて「インター校で学ぶことの大変さ」を親として痛感しました。



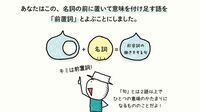



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら