実は日本技術の結晶「インドネシア製電車」の中身 中古車両導入は途絶えても「日本式」に高い信頼
同プロジェクトは住友商事及び日本車輌製造が受注し、1981年INKAが創業。日本から設備、資材を導入、日本車輌製造から多くの技術者が送り込まれ、貨車の国産化を支援した。
1982年には客車126両の国産化プロジェクトも同社が受注し、日本の国鉄43系を現設計とした客車をノックダウン生産した。これはその後、完全国産車としてマイナーチェンジを重ねながらも2010年代初頭まで製造が続いた。インドネシアが車両国産化を果たすことを鋭い洞察力で見据えた1970年代の商社マンの営業活動には感服するばかりだ。
1998年にはINKA・住友商事・日本車輌製造の合弁で、車両の設計支援などのエンジニアリングコンサルテーションを目的としたREKAINDO GLOBAL JASA(REKA)が設立された。しかし、世界情勢や日本経済の変化により、今ではINKAと日本車輌製造との関係性はだいぶ薄いものとなってしまったのは残念な限りだ。
また、INKAは日本のみならず、カナダ、ドイツ、フランス、アメリカのメーカーと連携し、技術を取り入れる例もあった。ただ、いずれも単発的なものに終わった。

日本の強みは「技術移転と教育」だ
1987年・1991年・1997年には円借款で調達した電車の一部の組み立ても実施し、この間に日立や東芝からも技術指導を受けた。ただ、当時は電機品を多用する電車に関しては、鋼体組み立てと装置艤装をするのみで、量産化に耐えうる車両を自ら生み出すことはできなかった。アジア通貨危機と、それに伴うスハルト政権の崩壊という外部環境にも影響されてしまった。
今回、192両という初の量産型電車の開発、製造が成功裏に導かれた背景には、INKAと日本メーカーとの歴史の積み重ねがある。今後、CLI-225型がインドネシアの通勤車両決定版として確固たる地位を築けるよう、装置のノックダウン生産が順調に進み、日系メーカーとの連携によってさらに拡大することを期待したい。

日本の強みは、鉄道開業以来の長い歴史と経験に裏打ちされた技術移転、技術教育にある。ODA案件として進むジャカルタMRTプロジェクトも、日本製品をそのまま売るのは通用せず、前述した「TKDN」=国産化比率をいかに高められるよう提案できるかが勝負になってくるだろう。日本がINKAとの関係性を継続的に築けるかがカギになってくる。

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






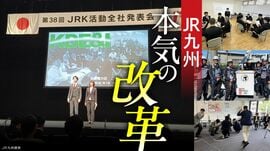

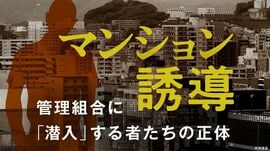




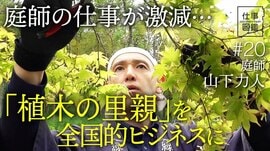


















無料会員登録はこちら
ログインはこちら