実は日本技術の結晶「インドネシア製電車」の中身 中古車両導入は途絶えても「日本式」に高い信頼
また、インドネシアでは工場の稼働率に応じて設計者や作業員が解雇されてしまうために製造品質の引継ぎが難しく、今回のプロジェクトで最も苦労した部分だという。工程管理も、マスタースケジュールはもちろんあるものの、造りながら考えて決めるインドネシア式の日取りになるため、数日前にならないと確定しないことも多い。「日本メーカーの製造指導、試験協力などに対する依頼がずれていくのを申し訳なく思う」と江本氏は言う。
それでも、受注から第1編成の出荷まで24カ月という契約納期を守り、最初の1本は3月17日に工場を出場、19日から日中に本線上での試運転がスタートした。
日本企業にビジネスチャンスはあるか?
「INKAの従業員平均年齢は29歳未満ともいわれており、納期確保などへのパワーは日本では見られないくらいの勢いがある。教えれば、議論すれば手応えが返ってくる」「INKAは東南アジアで唯一、車両の設計から製造・サービスまで一貫してユーザーへのサービスが提供できる会社。日本でわれわれが築いてきたのと同じく、やがて技術を習得して、自立して新規車両も国産化率を高めていくのではないか」と江本氏はINKAの今後に期待する。

一方で、国産化率を高めるうえでの課題もある。素材メーカー(ステンレス、絶縁物、特殊鋳物など)や、半導体を中心とした電機品などのサプライヤーが国内に育っていないからだ。
江本氏は「INKAはジャワ島最東端、バリ島のすぐ西にあるバニュワンギに新工場を開設した。CLI-225型も5本目以降の生産は新工場に移行する。敷地は大半が空き地になっており、このようなサプライヤー会社のJV設立も視野に入れれば日本からのビジネスチャンスがあるように思う」と語る。
INKAの成り立ちは1979年、当時のインドネシア国鉄向け貨車400両の政府調達にて、韓国やルーマニアの競合他社に入札価格で太刀打ちできないと踏んだ住友商事がインドネシア運輸省に対して国産化を提案したことに端を発する。この入札は結果的に流れ、同国政府は貨車の国産化プロジェクトに舵を切った。






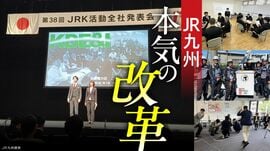

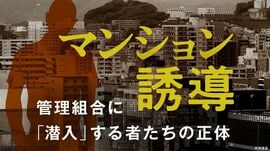




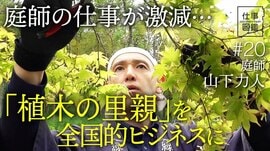


















無料会員登録はこちら
ログインはこちら