実は日本技術の結晶「インドネシア製電車」の中身 中古車両導入は途絶えても「日本式」に高い信頼
この間、INKAはインドネシア国内向けにステンレス製客車、電気式気動車、LRTと大量の受注を果たしていた。しかし、品質確保への意識はあるものの体系的、組織的な取り組みが不十分な状況で、江本氏にとって歯がゆい状況もあった。
そんな中、2022年にはジャカルタ首都圏向け通勤電車製造に関する覚書がKCIとの間で結ばれた。これを前提にシュタッドラー社とINKAのJV契約も結ばれていたが、それが一転し日本仕様での製造となった。「(中古車両として導入された)205系の信頼性・保守の容易性に対するKCIの強い意向があり、2023年3月にステンレス車体・JIS規格適用の新車両192両の正式契約となった」と江本氏は語る。

「日本式」が通らない場面も
江本氏はさっそく、安全性や信頼性の高い主要システムの導入(主回路、補助電源、ブレーキなど)、キーコンポーネントの採用(連結器、空気ばねなど)を決め、日系メーカーからの製品調達支援を行った。
同時に、INKAにとって品質確保のうえで最も重要な部分である、ステンレス車体の製造品質向上のための技術指導を実施。これは総合車両製作所(J-TREC)が構体の製造技術を支援した。そして、主要電機品のノックダウン製造(11本目以降、東洋電機製造)を契約。また、車両納入後のKCIへの保守・修理のローカルサービスの展開にも重点をおいて指導してきた。

もちろん、日本式が全て通用するわけではない。「JIS規格で契約しているが、やはりインドネシア運輸省のレギュレーションを優先しなければならない」と江本氏は言う。具体的には、床下の車両限界が日本より狭いことによる保守性の低下や、保安装置がないため正面衝突の可能性を考慮しなければならないことに伴う車両重量の増加、そして機関車並みの軸重差4%以内という厳しい基準(日本の電車は10%)に対応せざるをえなかったという。






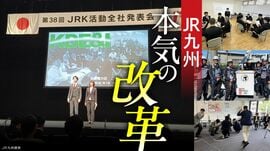

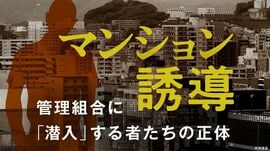




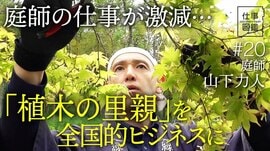


















無料会員登録はこちら
ログインはこちら