実は日本技術の結晶「インドネシア製電車」の中身 中古車両導入は途絶えても「日本式」に高い信頼
インドネシア側の立場から、国産通勤電車プロジェクトを支えてきた日本人エンジニアの存在も忘れてはならない。2018年2月からExpert Staff of Development DirectorとしてINKAに在籍する江本隆氏だ。
江本氏は1973年に東芝の交通部門に入社し、電車用半導体制御装置の開発を担当。主に電車用主回路システムとブラシレスMG(補助電源装置)の開発・商品化に従事した。現在、ジャカルタで中古車両が大量に活躍する国鉄(JR)205系電車の主回路システムの原設計も担当しており、205系の生みの親の1人ともいえる存在である。
海外では、1992年の韓国・果川線交流電化プロジェクトを皮切りに、米国・カナダ案件を経験後、2003年にはODAのマニラ2号線プロジェクトで車両システムプロジェクトマネージャーを担当。これをきっかけに、日本の鉄道システムの東南アジア向け輸出を目的とした規格づくり「STRASYA under KISS & Rail」の立ち上げに参画。台湾高速鉄道プロジェクトにも関わった。

日本人技術者が支える「日本式国産車」
「205系や『STRASYA』が実現したジャカルタMRTと、人生の作品がここインドネシアに集結しているように思う」と語る江本氏のINKAとの付き合いは、東芝在職時代の1998年に客車用空調案件で同社を訪問したことに始まる。その後、スハルト政権時に「国民電車」として計画されていたインドネシア標準通勤電車KRLIのステンレス車体とVVVFインバーター制御による駆動システム開発を日本車輌製造と共同で技術支援した。

この当時に関わりのあったINKAのエンジニアが同社幹部になり、声をかけられINKAへの入社を決めたという。
「当初の役割は通勤電車の製造限定というわけではなく、将来的な高速鉄道・準高速鉄道向けの構想を支援するとともに、電車や電気式気動車の駆動システム、SIV(補助電源装置)の技術支援を担当していた」と江本氏は言う。






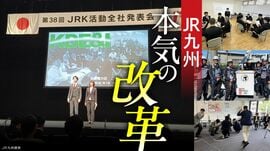

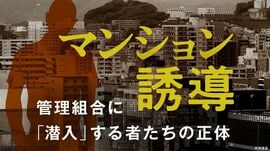




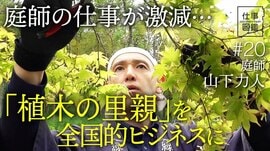


















無料会員登録はこちら
ログインはこちら