ここにあるのは、一種のフードナショナリズム(食の自文化中心主義)である。「内向き」といえば、そうかもしれない。だが、お金と時間が限られる中で簡単に気分が上げられるものが美味しい食事であるのもまた事実なのである。
ある民間シンクタンクの調査では、「食事で幸せな気持ちになったことはありますか?」という設問に9割以上の人が「ある」と回答している(食欲の秋に、幸せになれるレシピで幸福体質へ /2023年10月12日 /100年生活者研究所)。
ドーパミンやオキシトシンなどの「幸せホルモン」は、一定の強度がある運動、愛情を感じる人やペットとのスキンシップなどで得ることができるが、美味しい食事は最もハードルの低い「幸せホルモン」の放出方法といえる。なぜなら、ドーパミンは、食事の際に2度放出されることが明らかになっているからだ。1回目は食べ物を口に入れたとき、2回目はそれが胃に到達したときである(Food Intake Recruits Orosensory and Post-ingestive Dopaminergic Circuits to Affect Eating Desire in Humans/2018年12月27日/National Institutes of Health)。
長期停滞による食への相対的な関心の増大と、それに伴うフードツーリズム的な帰属意識の高まり、幸福感の重視……これらの一つひとつが、食に対する今日的な関心のあり方を形作っており、広義の食の安全についての認識や態度を決定する要因として力を持つに至っている。
このような分析を踏まえると、今回の騒動をはじめとして、食べ物をめぐる不祥事はますます強烈なハレーションを起こすものになっていくだろう。
無理がある「サービスと安全性の両立」
加えて、無視できないのが、社会学者のウルリヒ・ベックが「危険社会には、『不平等』社会の価値体系に代わって、『不安』社会の価値体系が現れる」と主張した「不安の共有」である(『危険社会 新しい近代への道』東廉・伊藤美登里訳、法政大学出版局)。
ベックは、「安全というユートピアは消極的で防御的である。ここでは、『良い物』を獲得することは、もはや本質的な問題ではない。最悪の事態を避けることだけが関心事となる。(略)危険社会の目標は、すべての人々が毒物の被害をうけなくてもすむべきだ、というものである」と述べたが、この「毒物」には心身の健康を害し得るありとあらゆる物質が含まれるとみていい。
続けてベックはいう。「階級社会の原動力は、『渇望がある』という言葉に要約できるとしたら、危険社会を進展させる運動エネルギーは、『不安である』という言葉で表現できよう。
つまり、危険社会では、階級社会にみられる欠乏の共有に代わって、不安の共有がみられる。この意味で、危険社会という社会形態の特徴は不安からの連帯が生じ、それが政治的な力となることにある」と。
物価高やステルス増税などによって国民生活が厳しくなっている現状を考えると、今後もよりコスパのいい食事が求められ、食による幸福感の追求が進むことだろう。しかしながら、そもそも一般論として、そのようないいとこ取りのサービスと安全性を両立させる発想には相当無理がある。

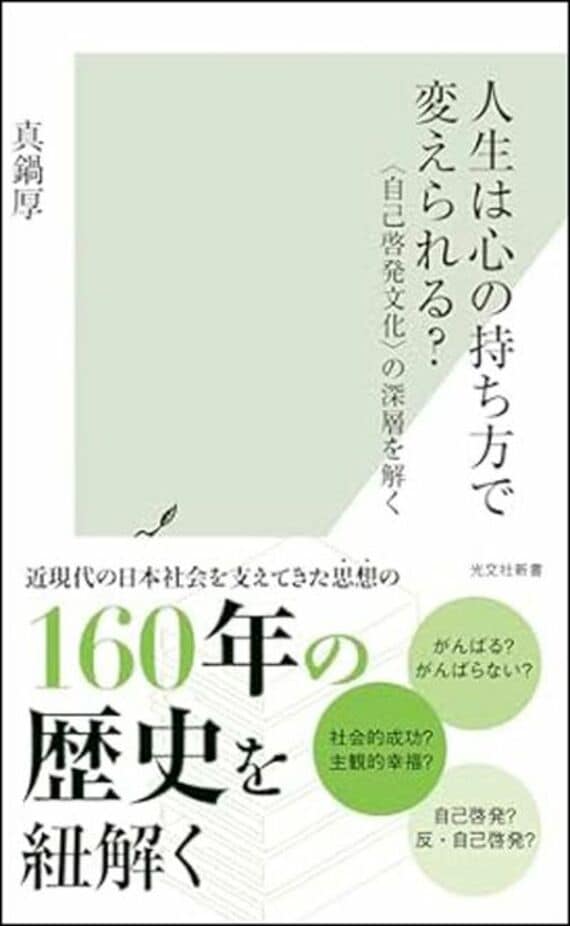






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら