大河ドラマ主役「蔦屋重三郎」現代の"ヒットメーカー"との共通点 作家たちとの交流で大事にしたこと
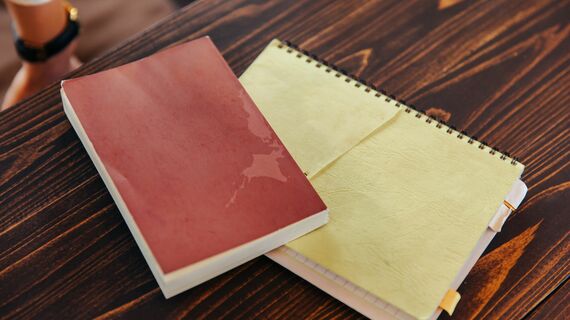
黄表紙ブームだった江戸時代
黄表紙(江戸時代中期以降に数多く出版された絵を主とする小説。黄色の表紙であったことから、黄表紙と呼ばれた)を1775年から1782年頃まで牽引してきたのが、戯作者(通俗作家)の恋川春町や朋誠堂喜三二、伊庭可笑などでした。
それから、1783、1784年(天明3年・4年)頃になると、山東京伝や四方赤良(大田南畝)、志水燕十といった実力派の戯作者が、黄表紙業界に参入。業界は、更に熱を帯びてきます。
そうなると、当然、黄表紙の出版点数も右肩上がりとなり、天明3年・4年には、それぞれ、84点、92点もの黄表紙が刊行されることになるのです。
天明元年(1781)が69点、天明5年(1785)が50点ほどということを考えれば、天明3年・4年は、黄表紙業界のピークと言えるのかもしれません。
黄表紙に限らず、書籍が売れるか否かの、1つの要因は、戯作者にかかっています。いい戯作者がいい作品を書けば、書籍は売れる可能性が高い。よって、版元による、戯作者争奪戦も起きていたようです。
江戸時代後期の著名な浮世絵師・戯作者の山東京伝は、天明4年頃までは、鶴屋(江戸時代初期に江戸で出店した老舗版元)と準専属的関係を結んでいたと言われますが、天明5年頃から、蔦屋重三郎が、それに待ったをかけたとされています。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら