利用に応じて水道料金を負担するのは当然だ。一方で2022年度というと、まだコロナ禍の影響で食費にも事欠く人たちが少なくなかったタイミングでもある。そうした中、容赦なくライフラインを止めるような政策は公正といえるのか。ユウタさんは水道が止まるたび、アルバイト先の水道水を飲んでしのいだという。
ネットで散見される「マイノリティの特別扱い」
平等と公正について。私が何年か前にその違いを表すイラストを見たとき、目から鱗が落ちる思いがした。

就職氷河期世代、しかも女性である私の足元にはいくつの木箱があるのだろう。一方でもっと長い目でみれば、木箱は決してゼロではないとも思った。前の世代の人たちが公正な社会の実現のために努力を続けてくれたおかげだ。
しかし、最近はSNS上を中心に、公正であろうとすることへの風当たりがかつてなく強まっているとも感じる。彼らはよく「マイノリティの特別扱い」「マジョリティへの逆差別」「行き過ぎた多様性」といった言葉を口にする。インボイス制度に反対する事業者への批判もこうした空気を反映しているようにみえる。
全員が野球を見られる社会をすぐに実現することは難しい。しかし、今まで続けてきた木箱を分け合う努力をなぜ今止めるのか。その理由が、私にはわからない。
ユウタさんは自身のことを「物売りの人」と呼ぶ。「コロナ禍でミュージシャンや俳優などの苦境はマスコミでもよく取り上げられましたが、僕らのような物売りはほとんど注目されませんでした」と振り返る。
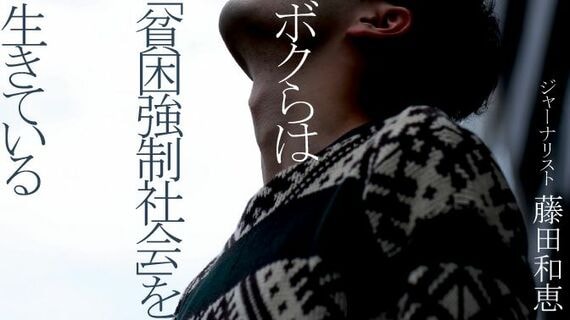
今も売り上げはコロナ禍前の半分ほど。インボイス制度は負担軽減措置が取られているが、いずれその影響は本格化するだろう。ポストコロナといわれる現在も「ダメージから脱することができずにいる人たちがいることを忘れないでほしい」とユウタさんは願う。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら