そうして過ごしているうちに、住んでいた邸が焼けてしまった。ただでさえつらい境遇に、ますます不運が重なり、あまりのことに宮は失望し、移り住む適当なところも京に見つけられなかった。宇治というところに風情のある山荘を持っていたので、そこに移ることとなった。すでにあきらめた俗世であるが、いよいよ住み馴れた京を離れるのを宮は悲しく思わずにはいられなかった。
網代(あじろ(川に竹や木を組み立てて魚を獲るしかけ))の設けてあるあたりに近く、水音も耳につく川のほとりで、静かに暮らしたいという願いにそぐわないところもあるが、仕方のないことである。花や紅葉、水の流れも、心をなぐさめるよすがとしながら、以前にもましてもの思いに沈んでばかりいる。こうして世間と離れて引きこもってしまった野山の果てでも、もし亡き妻がいてくれたらと思い出さない時はないのである。
見し人も宿も煙(けぶり)になりにしをなにとてわが身消え残りけむ
(愛した人もともに暮らした家も煙となって消えてしまったのに、なぜ私だけが消えず生き残っているのか)
生きている甲斐もないと、亡き人を恋い焦がれている。
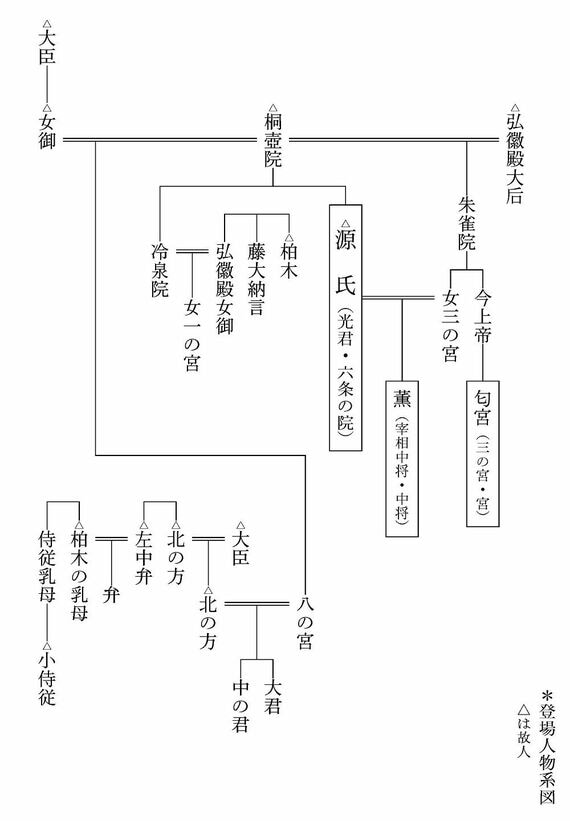
一途に出家することはとてもできない
京から山また山を隔てた宇治の住処(すみか)に、いよいよ訪ねてくる人もいない。身分の低い下人や田舎じみた山賤(やまがつ)たちがときたま親しく参上し、仕えている。峰の朝露の晴れる時もなく日々暮らしているのだが、この宇治山には聖然とした阿闍梨(あじゃり)が住んでいる。学問に秀でていて、世間の評判も軽くはないのだが、朝廷の法要にもめったに出仕することもなく引きこもっている。この宮がこうして近くに住み、さみしい日々を暮らしながら尊い修行を積み、経典を勉強しているので、阿闍梨は殊勝なことだと敬意をもって始終邸に足を運んでいる。阿闍梨は自身が長年学んできた数々の仏の教えの、深い意味を宮に説いて聞かせ、いよいよ現世がかりそめのはかないものであると教えるので、
「心だけは極楽の蓮(はちす)の上にのぼったように、濁りのない池にも住めそうに思うけれど、こんなにも幼い人たちを見捨ててしまうのが気掛かりなばかりに、一途に出家することはとてもできないのです」、宮は心の内を打ち明ける。
この阿闍梨は冷泉院にも親しく仕えていて、お経などを教えている人だった。京に出たついでに冷泉院に向かい、いつものように院がしかるべき経典などを読んで、質問をした機会に、
「八の宮さまはじつに聡明な方で、仏教の学問にも造詣が深くていらっしゃる。こうなるべき前世の因縁からお生まれになった方なのでしょう。心底から悟り澄ましていらっしゃるところなど、真の聖のご心境と拝見いたします」と話した。
「まだご出家はしていらっしゃらないのか。俗聖(ぞくひじり)などと、ここの若い人たちがあだ名をつけているそうだが、殊勝なことだ」と院は言う。

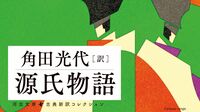


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら