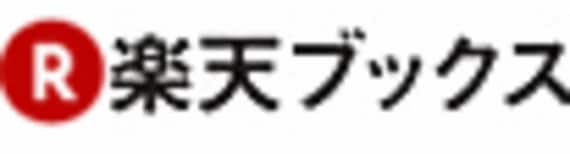自由論 ジョン・スチュアート・ミル著/山岡洋一訳 ~多数派による少数派への専制に警鐘を鳴らす

自由かつ多様であることが、個人の活力や多様な変化、そして独創性を生む。つまり少数派に寛容な社会がより発展する。評者は、規制緩和で経済活動を自由にすることが、人々の創意工夫を発揮させ、経済成長を高めると常々主張してきた。本書を読み、その意を強くした。
他者に危害が及ばない場合でも、放蕩など個人の望ましくない行動にどう対処するか。基本的に個人の責任であるが、社会にとって大事なことは、成人までの国民への教育であり、義務教育の重要性を説く。ただし、多様性を損なう恐れから、教育の実施機関が国であってはならないと強調する。優秀な官僚機構の存在が民間活動の足かせとなるため、外部からの官僚機構への監視と批判が必要と説く。現代にも共通する問題を多数取り上げる本書は、ハイエク『隷従への道』、フリードマン『資本主義と自由』と並ぶリバタリアニズム(自由主義)の三大古典の一つである。今回、大変読みやすい新訳が出版された。
国家の個人の行動への干渉は、個人の行動が他者に危害を加える場合にのみ正当化され、他者に危害を与えないかぎり個人の行動の自由は保障されなければならない。本書はこの「危害原則」を定式化したことで有名だが、ミルの生きた19世紀英国では、すでに議会制民主主義が確立しており、彼が警鐘を鳴らしたのは多数派による少数派への専制である。民主国家の個人への干渉の限界を明確化した本書の意義は、現在もまったく衰えていない。むしろ、国内の電力不足問題や欧米の財政・銀行問題など、「市場の失敗」を補正するはずの規制がより大きな「政府の失敗」をもたらしており、本書の意義は高まっている。
多数派にとり少数派は煩わしい存在である。しかし、だからこそ社会は味わい深い。
John Stuart Mill
1806~73。英国の哲学者、経済学者。19世紀を代表する功利主義者。著名な哲学者の父ジェームズ・ミルから英才教育を受けただけで、学校教育は受けていない。17歳から東インド会社に勤務。会社解散後の65年には下院議員に選出されている。
日経BPクラシックス 1680円 259ページ
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら