村上春樹『風の歌を聴け』が描く戦後日本の虚無感 「日本的なるもの」の喪失を描いた透明な文学
柴山:面白いのは、小説のなかに突然、Tシャツの絵が出てくるでしょ。好意的に解釈すると、これも伝えたいんだと思うんですよ、言葉にしにくいイメージを。「僕」の時代はこんな感じだった、と。
川端:ああ、突然下書きみたいな絵が出てきますね。びっくりしました。

柴山:あと、これまで読んできた過去の作家の要素がいろいろ入っていると感じましたね。この異様な構築性は三島っぽいし、自意識の問題をあれこれ書いてるのは「第三の新人」を思わせるし、謎を謎のまま話を進めていくところは太宰のようでもあって、全体のテイストはアメリカ小説のようでもある。だから、村上春樹って文学史をものすごく研究している人なんじゃないかという印象を持ちました。過去の要素を取り込みながら、独自の世界を作ろうとしているという。
浜崎:ものすごく褒めましたね。
柴山:最後にもう一つ言うと、これまでの文学って、インテリの自意識を描いてたように思うんですが、ここで描かれてるのはもっとはっきり、都市生活者の自意識ですよね。それぞれが自分の問題を抱えているんだけど、それをあけすけに語ったりせずに、それぞれがそれぞれの横を通り過ぎていくみたいな都市生活者の感覚を肯定的に描いている。そこが新しいと感じるゆえんなんだけど、こういうふうに肯定しちゃっていいのかなという疑問は残る。まあデビュー作だから、この先の展開もいろいろあるんでしょうけどね。
もう少し言うと、これって価値相対主義にかなり近いですよね。西部(邁)先生は絶対に認めないでしょうね、この世界は。弁証法がないというか、AとBで異なる見え方をしているのであれば、議論ですり合わせてお互いの納得を得るというふうに進まずに、ただすれ違って終わってしまうから。この小説は、鼠が持ってる世界と、僕が持ってる世界と、女の子が持ってる世界は、ライプニッツの「窓のないモナド」のように互いに重ならないんですよね。それが物足りないと言えば物足りないし、これはこれで成立していると言えば成立している。
世の中への破壊願望が薄れた80年代の気分
川端:僕も、印象は意外と良かったですね。村上春樹は本作を入れても3、4作ぐらいしか読んだことなくて、『ねじまき鳥クロニクル』とか『羊をめぐる冒険』とかタイトルは一応覚えてるんですが、ストーリーを思い出してみようとすると全く思い出せない。

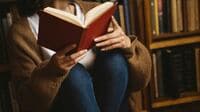































無料会員登録はこちら
ログインはこちら